こんにちは。とらすけです🐯
»プロフィールはこちら
我が家の息子は小4で学校へ行けなくなり、小6まで完全不登校。
中1では希望のフリースクールに週1回通学。
現在は中2になり、自分の力で勉強がしたいと、人生を開拓中です。
▼我が家のこれまでの不登校ストーリーをまとめた記事はコチラ▼
【不登校実体験ブログまとめ】小4〜中2の4年間の記録を一気読み!(全話リンク付き)
▼勉強に関する過去記事はコチラ▼
「【不登校】「勉強の遅れ」はどうする?不登校の子が勉強に取り組むために必要なこと」
さて今回は【過干渉】をテーマに、私が過干渉を辞めたことで、息子に現れた変化について書いていきたいと思います。
私は超がつくほどの過干渉な母親だったのですが、不登校と向き合う中で【過干渉を辞める必要】に迫られ、数年かけて手放してきました。
その結果、息子に良い変化がたくさん起こりました。
私、過干渉気味かな…とお悩みの親御さん。
過干渉を手放すことで、
・子から親への信頼が回復
・良好な親子関係が築ける
・子どもが自分軸で人生を考えるようになる
・子どもが動き出す
こんな変化が起こるかもしれません。
この記事が、今不登校に悩んでいる親御さんの参考になれば嬉しいです。
▼前回の記事はこちら▼
【不登校】子どもにイライラしない親になるために私が実践した7つのこと
▼我が家のこれまでの不登校ストーリーをまとめた記事はコチラ▼
【不登校実体験ブログまとめ】小4〜中2の4年間の記録を一気読み!(全話リンク付き)
▼私の毒親経験談▼
【不登校母の経験談】毒親育ち・毒親だった私の経験談まとめ(全3話)
自分の過干渉に気づくことからスタート

私が【過干渉】という言葉を初めて知ったのは、前回の記事で紹介した道山ケイさんの思春期子育てを学んだ時でした。
過干渉が何かを知れば知るほど、まさに自分のことで…
衝撃を受けたことを覚えています。
それから数年、過干渉をやめることを意識して過ごしてきました。
その結果、自分の気持や感情を言葉で表現すことが苦手だった息子に、すこしずつ変化が現れたのです。
・不登校の原因となった担任からの叱責事件について、自分の口から話をしてくれた。
・これまで溜め込んでいたネガティブな感情や不満を、自分の言葉で話すようになった。
・「◯◯に行きたい」「◯◯がしたい」「◯◯を買ってほしい」と、自分の願望を言葉で言えるようになった。
もちろん長い目で見ると、もっとたくさんの変化がありましたが、
子どもが自分の思っていることを、自分の言葉で話してくれるようになった
これが一番の大きな変化だったかもしれません。
子どもが親に、安心して自分の考えや思いを話せること、それは「良好な親子関係の土台を築いていくこと」につながっていきます。
過干渉とは?
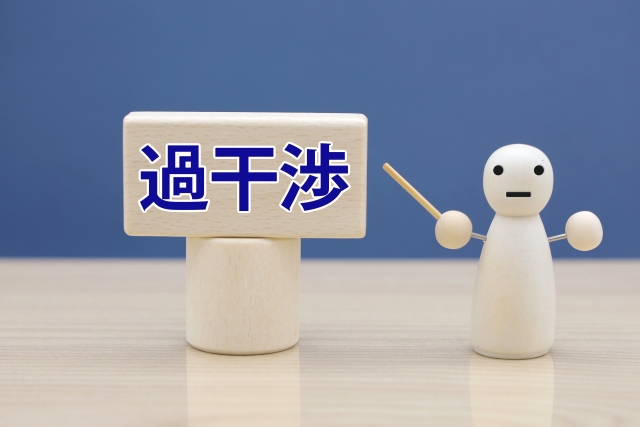
過干渉の意味
まず初めに、みなさん【過干渉】ってどういう状態かわかりますか?
ChatGPTに過干渉の意味を聞いてみました。
過干渉とは
本来は子どもが自分で考え、選び、経験していくべき領域に、親が過度に口を出したり先回りして行動してしまうことを指します。
一見「子どものため」「愛情から」と思える行為でも、実際には子どもの主体性や自立心を奪ってしまうことがあり、結果的に自己肯定感の低下や親子関係のすれ違いにつながることもあります。
具体的にはどんなこと?
【本来は子どもが自分で考え、選び、経験していくべき領域】というと…
・勉強
・習い事
・持ち物、服装の選択
・時間の管理、過ごし方の選択
そんなことが思い浮かぶでしょうか。
子どもは失敗をすることで成長していく
上で挙げたようなことについては、本来、子ども自身の課題であり、大人の課題ではありません。
(発達に凸凹がある子の場合、苦手なことについてはスモールステップでサポートしてあげることが必要な場合もありますが。)
人間は本来、トライ&エラーを繰り返しながら成長していくものですよね。
子どもなりに
やってみた!
↓
うまくいかなかった
↓
「これじゃいけないな…。次はこうしてみようかな?」
「またやっちゃったな…。自分はこういうところがあるな…(自己分析)。」
そんな風に、失敗を繰り返して遠回りをしながら、その子なりのペースで気づきを得て成長していくんだと思うんです。
(実際に、私が過干渉を辞めた後の息子は、そのように成長しています。)
大人は自分に都合のいい「最短ルート」を求めてしまう
でも、私達大人は、自分が失敗した経験があるから、失敗の先がどうなるかがわかっています。
だから、子どもに「最短ルートでの成長・成功」を求めてしまう。
本来は「遠回り」にこそ、子どもの成長につながる要素がたくさんあるのに、「こうしとけば上手くいくから、こうしときなさい!」と、子どもが自分で考える前の段階で先に口出しをしてしまいます。(無意識ですが。)
そのほうが自分(大人)が楽だし、世間からの評価も上がることを知っていますからね。
やり方がわからない子に対して、アドバイスやヒントを伝えてあげる、説明してあげることも、時には必要だと思います。
でも最初は、少し伝えるだけのつもりだったのに、気づけばその後もずっと、子どもに口出しし続けてしまっていること、ありませんか?
すぐにやらない(成長しない)子どもに対して黙って見ていられなくなる…
注意が増えていき、口出しが過度になる…
気づけば【過干渉】になっていること、ありませんか?
過保護とは違うの?

一方で…
「過干渉」という言葉を知った時に、ふと思いました。
「過保護」と、どう違うんだろう?と。
こちらもChatGPTに聞いてみました。
過保護とは
子どもが本来は自分の力でできることまで、親が先回りして守ったり手助けしてしまうことを指します。
危険や失敗から過度に遠ざけようとするため、子どもが自分で挑戦する機会を失いやすくなります。
一見「優しさ」や「守ってあげたい気持ち」からの行動でも、結果的に子どもの成長や自立を妨げる原因になることがあります。
【過干渉】と【過保護】の違いまとめ
似ているようで…少し違う…
わかるような…わからないような…
わかりづらいですよね。
ChatGPTにさらに整理してもらうと、こんな感じでした。(あくまでも1例です。)
| 過干渉 | 過保護 | |
|---|---|---|
| 定義 | 子どもが自分で考え・選び・行動すべき領域にまで親が口を出すこと | 子どもが自分でできることを親が先回りして守ったり手助けすること |
| 例 | 「宿題やった?」「この服を着なさい」など細かく指示する | 忘れ物を親が常に確認・持っていってあげる |
| 背景 | 親の不安やコントロール欲から出やすい | 子どもを守りたい・失敗させたくない気持ちから出やすい |
| 子どもへの影響 | 自主性・自己決定力が育ちにくい | 挑戦する力・失敗から学ぶ力が育ちにくい |
ふむふむ。なるほど。
【過干渉】→親の不安やコントロール欲から出やすい
【過保護】→子どもを守りたい気持ちから出やすい
このポイントで判断すると、違いが少しわかりやすいかもしれません。
でも「失敗から学ぶ」という意味では、過干渉も過保護も共通しているところはあるのかな…と。
これは過干渉?過保護?と考えることよりも、
「脱・過干渉」、「脱・過保護」どちらにせよ、
・子どもに失敗させる勇気を持つ
・子どもが自分で考えて動くのを待つ覚悟を決める
・子の課題と親の課題を分けて考える(課題の分離)
・親は自分の課題に集中する
ここがポイントだと思います。
道山流思春期の子育て法での定義は?
ちなみに。
私が前回の記事でご紹介した、道山ケイさんの「思春期の子育て法」では、道山さんなりの言葉で「過干渉」と「過保護」の定義や違いについて解説されています。
著作権の関係もあるので、私からはお伝えできませんが、私はその説明がすごくわかりやすく、腹落ちする説明が書かれていました。
もし、気になる方は、無料で冊子やメルマガが受け取れますので、試しに一度、道山ケイさんのサイトを見てみてください。→【道山ケイこどもの反抗期や不登校で限界の時の対処法】
私の過干渉・毒親経験談
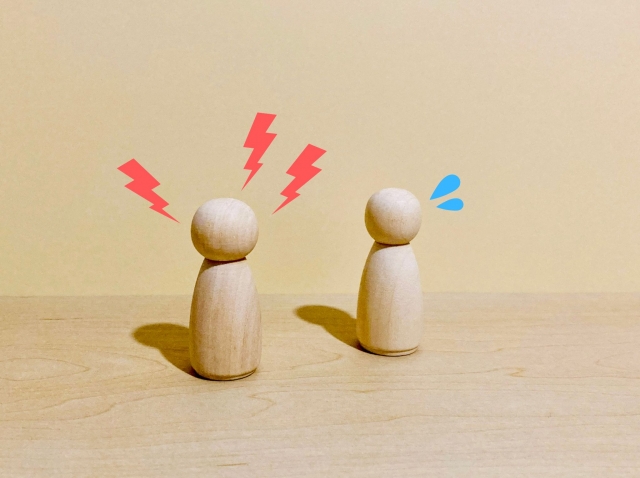
本当は、道山さんの定義で説明するととてもお伝えしやすいのですが、このブログでは引き続き、ChatGPTからの定義を元に、過去の私の過干渉母ぶりを振り返って生きたいと思います。
▼私の毒親経験談▼
【不登校母の経験談】毒親育ち・毒親だった私の経験談まとめ(全3話)
当時、息子にどんな対応をしていた?
これはもう、あげるとキリがないのですが、思いつくところをザッと挙げていくと…
- 学校から帰ったらまず何よりも先に宿題をさせる
- ゲーム時間はきっちり管理(友達が来ていようが、1時間と言ったら1時間で切る)
- 9時までには寝る
- そのために、夕方からのタイムスケジュールが遅れないよう、ずっと注意&怒りっぱなし
- 遊びにいくのは宿題&やることをすべて終わらせてから
- 消しゴムをうまく使えない息子に、きれいに消せるまで何度でもやり直させる
- 字は綺麗に、丁寧に。汚い字は書き直し
- 嫌いなものも残さず食べるまでごちそうさまはダメ
- のんびりタイプの息子に対し、予定通りの時間に予定通りのことが終わってないと、終わるまでずっと注意をし続ける
- 子どもが喋る前に、自分(母)の意見を言って納得させる(押し付ける)
- 「あなたの問題だから、やらないならやらないでいいんじゃない?」といいながら、結局、その後イライラして口出しをする
……自分のことながら、怖すぎます……。
読むだけで息が詰まりますね。
こんな環境で息子は、母からの圧に耐えながら頑張っていたんだなあと思うと、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。
私ほどひどい母はなかなかいないかもしれませんが、思い当たる節がある人もいるんじゃないでしょうか?
私の過干渉の理由
私はまさに「自分の不安を解消してもらうため、自分のコントロール欲のため」に息子に口出しをしていました。
子どもの将来のためと言いながらも、元を辿ると、
・自分のスケジュールを乱されたくない
・自分の仕事を増やされたくない
・先生や世間からの(私に対する)評価を下げたくない
という自分本位のコントロール欲のためでした。
結局は「自分のため」に子どもをコントロールしようとしていたのです。
焦らせずに「待ってあげる」ことで子どもは成長する
本来子どもは、その子なりのペースで成長してこそ、その子らしい花を咲かせてくれます。
なのに私は、
「早く芽を出しなさい!まだなの!?早くしてくれないと私が困る!」
と、息子の成長ペースなどお構いなしでした。
その子のタイミングを信じて待ってあげていれば、その子らしい綺麗な花が咲くのに、
「そんなことはいいから、とりあえず、みんなと同じ色と形の花を咲かせなさい!」と、
つついて、焦らせてばかりいました。
待ってあげることができなかったのです。
脱・過干渉のために必要なのは【他人軸】を手放すこと
私の過干渉は、
【過干渉】=【子どものペースを無視し、その子なりの成長を待ってあげていない状態】
でした。
脱・過干渉後の今は、
【過干渉じゃない状態】=【その子なりのペースでの成長を、じっくり待ってあげらている状態】
になりました。
ここに至るために必要だったのは、
【世間からの目】【周りからの評価】という【他人軸】を手放すこと。
以前の私は、
・過干渉をしないといられない
・子どものペースを待てない
・コントロールしたくなる
これらは全て、世間からの評価を気にした【他人軸】で考えていることが原因だったのです。
過干渉をやめる決断

息子からの一言で過干渉をやめようと決断
そんな過干渉の塊だった私が、なぜ過干渉をやめようと思ったのか。
それは、不登校直後の息子に言われた言葉がきっかけでした。
当時息子は、不登校直後でメンタルが不安定。
混乱状態で、幻覚を見たり、「生きているのがつらい」と言っているような状態でした。
そんな中で、「母さんが怖い」「母さんが怒ることがストレスの一つ」とはっきり言われたのです。
本当にショックでした。
でも、気づけば毎日イライラして怒鳴ってばかりでした。
自分でもわかっていた。
でも私は変わろうともしなかった。
そんなことを何年も続けてきた結果、息子は私に安心して相談すらできないような、親子関係になってしまっていたのです。
担任から行き過ぎた叱責をされ、すごく怖かった、辛かったのに…
本来なら一番の味方であり、安心して相談できる存在であるはずの母親に不安な気持を吐き出せず、息子は、恐怖心・不安感・すべてのネガティブな気持ちをすべて自分の中に閉じ込めてしまい、うつ状態になりました。
そんな息子からの言葉、様子に直面し、
「目の前の状況を良くするには、息子を変えるのではなく、私が変わることが必要だ。」
そう確信したのです。
道山流 思春期子育て法と出会う
そんな時に見つけたのが「道山流 思春期子育て法」でした。
そこで、
不登校を解決することよりも、私が過干渉をやめ「親子関係の修復」をすることの重要さに気づいたのです。
我々親子にとって、まずは「私自身を信用してもらうこと」が最優先でした。
心が安心・安定して初めて、回復が始まります。
変えるべきは、子どもではなく「私自身」。
こんな私でも今からでも変われるかもしれない。
いや。
「変われるかも」じゃなくて、息子のために「変わらなければいけない」。
そこから、私の「脱・過干渉」の日々が始まりました。
自分をどう変えていったのか
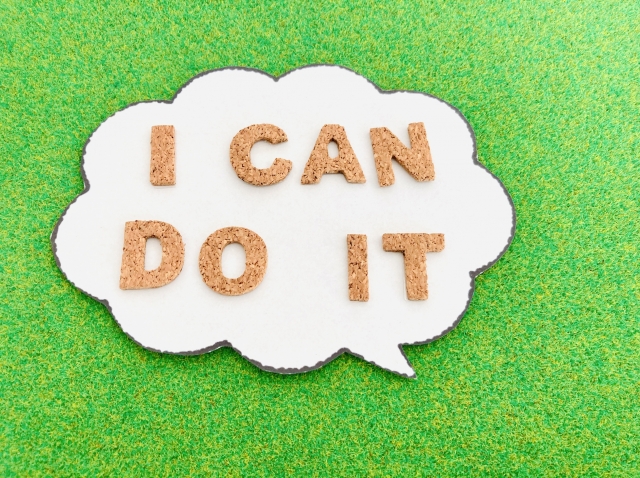
焦らなくていい、一歩ずつ進んでいこう
もちろん時間はかかりました。
決意して、「しばらく意識したらできるようになりました!」って、そんな簡単なものではありません。
何年もかけて、徐々に変わっていきました。
でも、最初はまず「意識をするところから」。
なんだかんだ言っても、自分自身が意識をして過ごさないことには、何も変わりません。
・口出しを1回やめてみる
・同じことを言うのを1回やめてみる
・1回、言わずに待ってみる
その回数を増やしていけば、少しずつでも変わっていけます。
「できなかった」ではなく「できた!」を見てあげよう
もちろん意識をしても、感情がついていかず、結局色々口出しをしてイライラしてしまうと思います。
時には、我慢した分、大爆発を起こしてしまうこともあるかもしれません。
そんな中でも、1日50回やってた過干渉な口出しを、今日は49回にすることができた!
それでいいと思うんです。
次の日また50回になっても、その後、48回だった日があったら、それだけでも前進。
48回もやってしまった…
ではなく
2回も減らせた!すごい!!
そう考えたほうが、同じ回数だったとしても気持ちが前向きになりませんか?
「できなかった…」ではなく「できた!」に目を向けてみましょう。
そんなことをしてるうちに、あれ?45回で済んだかも!なんて日が来ます。
小さな成功でいいので、自分のことをたくさん褒めてあげてください。
我慢したぶん、親のストレスは溜まる
でも、実際、口出しをせずに待つ・見守るって、そう簡単なことじゃないです。
最初は特に、我慢したぶん、おそろしくストレスが貯まります。
でも、それを解消するために過干渉を続けても良いことはないと、皆さんお気づきだと思います。
かといって、我慢の限界のたびに怒りを大爆発させるのも、子どもはもちろん、親御さん自身もすごく辛いと思います。(経験談…)
【物の手放し】で【脱・過干渉】ができた

私もずっと、我慢することによるストレスで苦しんでいたのですが、そんな時にXで「物を7割手放したらイライラしなくなった」という、とある不登校ママさんの投稿に出会いました。
それを機に物の手放しを開始。
物を手放しをし、物の少ない暮らしを始めたことで、私の意識が、いい意味で子どもに向かなくなりました。
「物を手放す」ことは「自分の持ち物と向き合うこと」。
実はそれは「自分と向き合う」ことにもつながっていくのです。
それを繰り返すことで、「他人がどう思うか(思われるか)」ではなく、「自分はどう思うのか」という【自分軸】で考えられるようになりました。
そして気づけば、【他人軸】を手放せるようになり、その頃には、子どもとの境界線がうまく引けるようになっていました。
子どもとの境界線を引き、自分自身が世間からの目や評価を気にしなくなったことで、子どもへの口出しをせず、子どものペースを見守れるようになったのです。
物の手放しについては、また別記事で紹介する予定ですので、またそこで熱く(笑)語りたいと思います。
口出しをしなくなったら本当に何もしなくなるのでは?

答え:一旦は何もしなくなります
とはいえ、とらすけさん。
そんな簡単に言うけど、これまで散々口出しをしてもやらなかった子に口出しをやめたら、もっとやらなくなりませんか!?
もっとやらなくなったら、困ります!
そんな声が聞こえてきますね…。
答えは
「はい。やらなくなります。」
です…。
ごめんね。
口出しをやめました→嘘のように子どもが自ら進んで勉強するようになりました!なんて、そんな魔法は残念ながらありません。
一旦は、本当に何もしなくなることは覚悟してください。
けど、それ以上に大事なことがある
でもね。
ここで思い出してほしいのは、なぜ過干渉をやめたほうがいいのか?というゴールです。
そう。
不登校解決以前に、心の土台となる「親子関係の修復」が大事
これでしたよね。
・自ら勉強する
・自分で考えて目標を立てる
・興味をもったことに取り組む
・外の世界へ足を踏み出す
子どもたちに、そうなってほしいんですよね。
じゃあ、そのために「今」必要なのは?
【良好な親子関係】なんです。
これが、子どもたちがいつか、自ら挑戦してみようと立ち上がる時の心の土台になるんです。
心の土台は基礎工事
この土台がグラグラしていると、安心して踏み出せません。
建物の基礎工事で考えてみてください。
基礎工事は建物が建ってしまえば目には見えません。
その家がとても素敵な外装・内装ならなおさら、とても魅力的で完璧な家に見えます。
でも基礎工事が適当だったら?
いくら見た目が良くても、ちょっとした地震でも崩れるかもしれない…。
そんな家では、毎日安心して過ごせませんよね?
心で考えると、困難や壁にぶち当たった時、土台がしっかりしていれば足にも力が入り、大変ながらも乗り越えるエネルギーを出せますが、土台が固まっておらず足元がグラグラしている状態では、力もはいらずエネルギーが出せません。
なので、今は、目先の「勉強しなくなる」「何もしなくなる」ではなく、「親子関係の土台を作り直すチャンス」だと考えて欲しいです。
土台が安定すれば、一時的には悪化したように見えても、子どもたちは目に見えないところで少しずつ回復し始めます。
すぐには効果が目に見えないので、何もしない子どもの様子をみているととても不安になると思います。
それを見て、また色々言いたくなるのが普通だと思います。
これはある程度は仕方がありません。
なので、過干渉をやめるにあたっては、
子どもではなく自分自身に目を向ける
これが大きなポイントになってくるかと思います。
繰り返しになりますが、そんな時には物の手放しが本当におすすめです。
また、物の手放しや物の少ない暮らしの効果についても記事にしようと思っているので、そちらの記事もぜひ読んでもらえたら嬉しいです。
過干渉を辞めた結果、息子に現れた変化

そんな葛藤もありつつ、過干渉をしなくなった結果、息子はどう変化したか。
- 自分の気持ちを話してくれるようになった
- ネガティブな気持ちも言葉にして言えるようになった
- 不登校の原因となった担任からの叱責事件の詳細を口に出して話してくれた
- 自分の意見や将来のプランを楽しそうに語るようになった
- 私の意見と違っても、そこでひるまず、自分の考えをしっかり伝えてくれるようになった
- 自信と根拠をもって自分の意見を言うようになった
- 自分の考えが間違っていた、甘かったと気付いた時は、素直にそれを認めるようになった
- 親子で冗談を言い合えるようになった
- やりたいことを見つけ、動き始めた
もちろん、過干渉を辞める以外にも、私自身が変わるために物の手放しなど他の取り組みもしていたので、過干渉をやめたことだけが理由ではないかもしれません。
とはいえ、この「脱過干渉」という頑張りがなければ、他の取り組みにもつながらなかったと思うので、その効果はとても大きなものであったと思います。
「母に自分の気持や意見を、言葉にしてはっきりと伝えることができる」
実はこれ、私自身が小さい頃から親に対してずっとさせてもらえなかったことでした。
なので、私にとって、息子がこれらのことができるようになったことは、本当に大きい意味があり、とても嬉しいことだったのです。
そして、これらのことをひっくるめて、
親子関係が驚くほどよくなった
そう感じています。
親子関係、信頼関係は、これからの長い人生の土台になっていきます。
不登校は大変なことばかりかもしれませんが、その分、自分自身と向き合うチャンス、親子関係を修復する大チャンスです!
どうせ大変な山であれば、頂上に登った時、下山する時に、より成長した自分、より楽しく会話のできる親子になってるほうが、嬉しくないですか?
今できていない自分、これまでできていなかった自分を責めるのではなく、より嬉しい自分、より楽しい親子に近づくために、一歩踏み出してみませんか?
▼私の毒親経験談▼
【不登校母の経験談】毒親育ち・毒親だった私の経験談まとめ(全3話)
まとめ
【過干渉】時代の私は、子どもの成長を【待つことができなかった】。
・子どもが喋る前に自分が喋る
・子どもの話を遮って、自分の意見やアドバイスを言う
・子どもができていないことはこと細かく注意する(できていることには目を向けない)
・自分の思い通りになるように子どもをコントロールしようとしていた
・子どもを待つことができず、常に焦らせ、急かしてしていた
・世間からの目・評価を気にして行動していた
過干渉を辞めて、【子どもが動くのを待つ】を意識して過ごした結果。
・親に自分の意見や希望を伝えてくれるようになった
・笑顔が増えて元気になってきた
・自分のペースで成長し、動き始めた
・自分の個性を大事にできるようになった
・親への信頼貯金が増えた(たぶん(笑))
・親に自分の気持や、ネガティブなことも話してくれるようになった
・親子の会話・笑顔が増えた
このような変化がありました。
これらを全てひっくるめると、
【心の土台】、【人生の土台】となる【親子関係】がよくなった
これに尽きるかと思います。
自分を変えることは、時には苦しく、大変なことではあります。
でも、それを乗り越えた先には、子どもと笑顔で過ごせる日々が待っていました。
もし、今の状況を変えたいと思っている方がいたら、私の経験談がヒントになると嬉しいです。
今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ではまた!とらすけでした🐯
▼前回の記事はこちら▼
【不登校】子どもにイライラしない親になるために私が実践した7つのこと
▼我が家のこれまでの不登校ストーリーをまとめた記事はコチラ▼
【不登校実体験ブログまとめ】小4〜中2の4年間の記録を一気読み!(全話リンク付き)
▼私の毒親経験談▼
【不登校母の経験談】毒親育ち・毒親だった私の経験談まとめ(全3話)
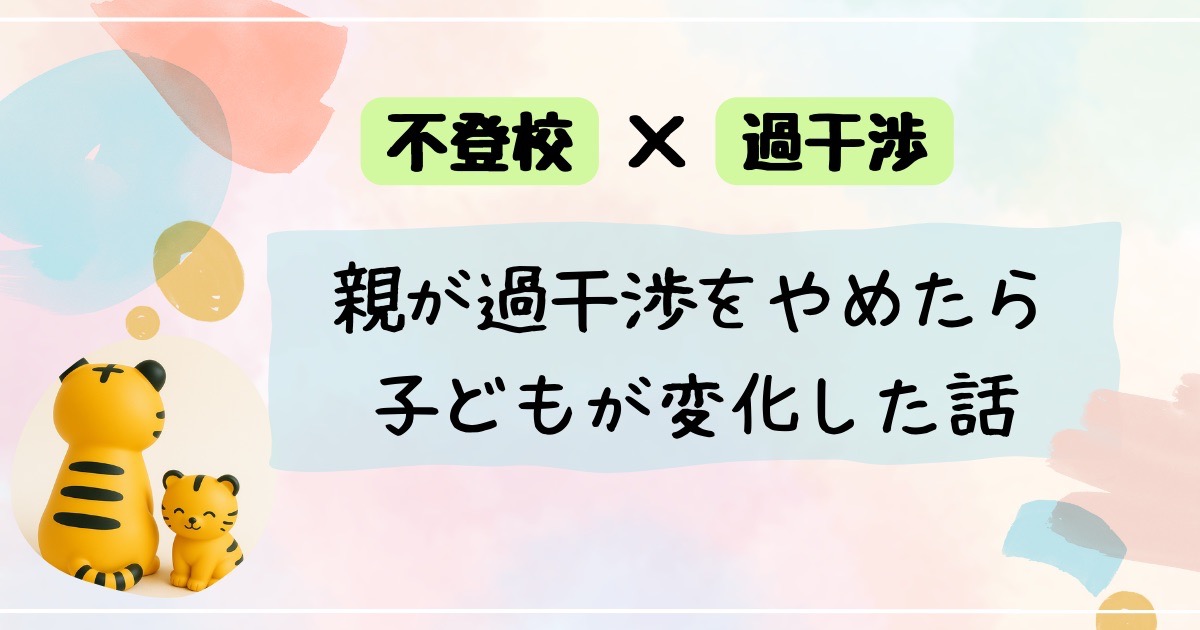

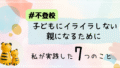
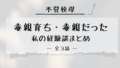
コメント