こんにちは。とらすけです🐯
»プロフィールはこちら
息子は小4で学校へ行けなくなり、小6まで完全不登校。
中1では希望のフリースクールに週1回通学、1年間継続しました。
そして現在中2。
自分の力で勉強をしたいと、フリースクールから新たな道へ切り替え中です。
小学校後半はほぼゼロ勉でしたが、今は自ら勉強をするまでに回復しました。
▼勉強に関する過去記事はコチラ▼
「【不登校】「勉強の遅れ」はどうする?不登校の子が勉強に取り組むために必要なこと」
ここまで書いてきた「経験談①〜⑬」では、不登校1年目、2年目の出来事を綴ってきました。
(👇過去記事の一覧は下にまとめています👇)
今回は、不登校3年目(小6)の記録をお届けします。
この時期は引き続き、安定した不登校生活を送っていました。
そんな中での「私自身の生活の変化」と、
「それに伴ってまた一歩大きく動き出した息子」
について書いていこうと思います。
今回も、悩んでいる誰かの参考になったら嬉しいです。
↓【不登校経験談】過去記事はコチラ↓
我が家の不登校経験談①~不登校になるまで~
我が家の不登校経験談②〜不登校の原因となった担任からの叱責〜
我が家の不登校経験談③〜スクールカウンセラー〜
我が家の不登校経験談④〜不安と焦り〜
我が家の不登校経験談⑤〜先生が変われば…期待と現実〜
我が家の不登校経験談⑥〜「生きているのがつらい」息子から届いたSOS
我が家の不登校経験談⑦〜母子ともに限界だった2学期の始まり〜
我が家の不登校経験談⑧〜発達検査でADHDが判明〜
我が家の不登校経験談⑨〜ADHD診断後に療育が見つからない!高学年・不登校のリアル〜
我が家の不登校経験談⑩〜通院をやめても、少しずつ前に進んでいた〜
我が家の不登校経験談⑪〜「学校以外の道」を探し始めた日々〜
我が家の不登校経験談⑫〜発達外来での絶望と、ペアレント・トレーニングという選択〜
我が家の不登校経験談⑬〜不登校2年目のリアル、ゲーム・昼夜逆転・親の葛藤〜
小6、不登校3年目。「笑顔でおはよう」が言えなかった私の選択

小6、不登校生活も3年目。
息子は相変わらず、ゲームとYouTube漬けの生活を送っていました。
深夜までゲーム――ではなくなってきたものの、毎日起きてくるのは昼過ぎ。
「夜眠れない」という問題はずっと続いていました。
「寝たいけど、眠れない」。
静かな部屋が怖い、目を閉じるのが怖いとよく言っていました。
電気をつけて寝てみたり、YouTubeで音楽を流しながら寝てみたり…息子なりに工夫もしていました。
でもどうしても眠れないと言うのです。
そんな状態を見て、私はつい“正論”を口にしてしまっていました。
「ゲームのブルーライトが悪いんじゃない?」
「太陽の光を浴びたほうがいいよ」
「もっと運動したほうがいいんじゃない?」――。
強制はしなかったけれど、
アドバイスという名の“大人の理想”を求める言葉は、
息子をますます追い詰めていたと思います。
本人も自分でもどうしようもなくて苦しかったはずなのに、それを否定される日々。
大人は「子どものため」「将来のため」と言うけど…
じゃあ自分が同じ状況になって、家族からそうやって責められたらどう思うか?
心は元気になるか?
できないことを「できるように」と言うたびに、
「今のままの自分じゃダメなんだ」と思わせてしまっていたと思います。
それは、回復のペースを遅らせることにも繋がります。
でも…
当時の私には、息子の状態をそのまま受け入れる“器”がありませんでした。
「どんな時間に起きてきても、笑顔で『おはよう』が言える親」には、そう簡単にはなれなかった。
人によって元々の性格、器の大きさも違う。
急に変わるのは難しい。
でも、このまま朝がくる度に、起きてくる息子の顔を見て嫌な気持ちになっている今の状況も苦しい。
“どうすれば自分と息子が少しでも楽に暮らせるか?”
「息子をどうにかする」のではなく、「自分にできることはないか?」に焦点を当てました。
私が選んだのは「子どもと程よい距離をとること」
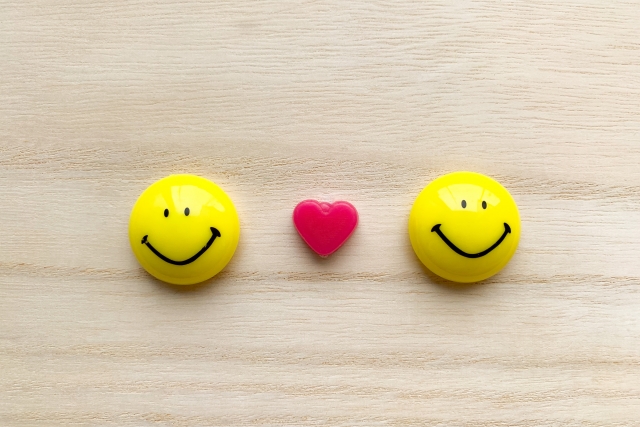
私は、息子が小6の夏からパートを始めました。
息子が起きてくる前に出社し、息子が起きてくる昼過ぎ以降に帰宅するようにしました。
これは、私自身のイライラを避けるためでもありました。
昼過ぎにリビングに出てくる息子を見ると、どうしても私は不機嫌な顔になってしまう。
息子もきっとそれを感じていたでしょう。
「またお母さん、機嫌悪いな」って。
そしてまた、「今の自分はやっぱりダメなんだ」と思ってしまう。
負のスパイラル…。
「お母さんが家にいたほうが安心して休める」タイプの子なら、家にいる選択をしたかもしれません。
でも、息子の性格や普段の様子を見ていると、家に誰もいない時間のほうが安心して休めてそうでした。
だったら、お互いのストレスが減らせる程よい距離を取るほうが良いのではないか。
――そう思ったのです。
その結果、パートを始めてから、私は息子に対して少し穏やかに接することができるようになりました。
不登校の正解は「子どもごとに違う」

よく
「不登校でも規則正しい生活が大事」
「朝は起こして夜は早く寝かせましょう」
といったアドバイスを見聞きします。
実際、それがうまくいくご家庭もあります。
でも、我が家のように、それが親子関係の悪化につながるケースもある。
大事なのは、「我が子にとってどうか?」を見極めること。
“我が家なりの正解”を、親子で模索し続けることなのだと思います。
私が4年間の不登校生活で大事にしていた土台は、
「親子関係の悪化だけは避ける」でした。
もともと我が家は親子関係がボロボロでした。
でも時間をかけて、少しずつ修復してきました。
今、息子が少しずつ外に意識を向けられるようになっているのは、
安心できる親子関係があってこそだと実感しています。
子どもには、子どもなりの回復のペースがあります。
自分から「そろそろ動いてみよう」と思えるタイミングがあります。
でも当然ながら、そのタイミングはその子によって違います。
その時が来るまで、「信じて待ってあげる」。
4年間不登校と向き合ってきて、そう感じています。
息子の「動き出したい」が見えた瞬間

そんなふうに、私が自分自身に目を向けられるようになった頃、息子が言いました。
「中学校からは、フリースクールに行ってみたい。見学に行きたい」
正直、すごく嬉しかった。
ただ、心のどこかで
「飽きっぽい息子のことだから、どうせすぐに気が変わるかもな…」
とも思いながら、オープンキャンパスへ行きました。
そこでは、入学にあたって筆記テストがあることも説明されました。
もちろん不登校の子たちがほとんどなので、「学力で合否を判定するわけではない」と言われたけれど、小6の時点で九九も忘れていた息子にとって、それは大きなハードルでした。
それでも息子は、家庭教師との週1回の勉強だけは、欠かさず頑張っていました。
(実は、一度は家庭教師も受けられなくなり辞めかけたこともあったのですが、それはまた別記事で書こうと思います。)
家庭教師の日以外は相変わらずゲーム漬けだったけれど、
【教科書を開き、鉛筆を持って、ノートに書く】
――それだけでも、私には涙が出そうなくらい嬉しい変化でした。
結局、息子は宣言通り、筆記テストを受けることができました。
入試当日、3教科のテストと面接を受けきった息子のは、とても自信に満ちた顔をしていました。
テスト自体は「全然解けなくてボロボロだった〜」と言いながら(笑)
でも、表情はとてもイキイキしていたのです。
かつての「生きる気力さえ失ってしまった息子」からは想像もできないほどの成長でした。
合格、でも「週1回から」の条件つき

結果は合格。
ただし、登校は週3を希望していたものの、まずは週1から始めましょうという条件がつきました。
息子はショックを受けていました。
でも時間が経つにつれて現実を受け入れ、4月からの登校を楽しみにするようになったのです。
この「ちょっとした挫折」すら乗り越えられたことも、心の回復が進んだ証拠。
1年前だったら、きっとその時点で崩れていたと思います。
結果的に、「週1でよかった」と息子は言いました。
「週1は人数が少ないし、落ち着ける。仲良くなりやすい」と。
大人からすると「たくさん通ってくれたほうが安心」と思いがちだけど、
子ども自身が安心して過ごせることが、その子にとっての“正解”なのだと改めて感じました。
卒業式には出なかったけれど、大切な思い出ができた

こんな感じで、小6の1年間は、比較的安定していた不登校生活でした。
そして、小6の不登校で親御さんたちが気になることの1つが、卒業式だと思います。
我が家は卒業式には出席しませんでした。
息子自身の希望です。
息子も私も、参加しないという選択に、不安も迷いもありませんでした。
私も「学校に辛い思い出がある息子にとって、卒業式に出ることで何かプラスになることってある?」と思っていました。
逆に、出ることで本人にとってマイナスになりそうなことなら山ほどありました(笑)
なら、出ない選択でいい。
でもその日の午後、学校が静かになってから、息子が心を許していた当時の担任の先生と、過去にお世話になった元担任の先生2人が出てきてくれて、校舎の廊下でこっそり卒業証書をいただきました。
私達親子にとっては、立派な厳かな式典よりも、ずっとずっと素敵なプチ卒業式でした。
息子の苦しみにずっと寄り添ってくれていた先生たちが、息子の卒業を心から祝ってくれた…
とてもあたたかく、心のこもった時間でした。
(これを書きながらも、涙が出てきます…。)
卒業アルバムは、写真も入れず、購入もしませんでした。
実際、息子の写真欄はグレーになっていたようですが、それを見た友達やお母さんたちも、それまでと変わりなく接してくれています。
そんなことで態度が変わるような友達は、別に付き合わなければいいだけだと思います。
(実際、そんな親子は本当にいなかったのですが。)
ちなみに私は、自分自身の卒業アルバムなんて見返したこともないし、正直いらないし。
卒業アルバムに関して何の執着もないタイプなので、息子が決めればそれでいいと思っていました。
(先生は少しさみしそうでしたが、それは先生の愛情だと受け取らせていただきました。)
誰かと同じ形を目指す必要はない。
その子とその家庭にとって“ちょうどいいかたち”が、きっとある。
今はそう信じています。
まとめ
小6・不登校3年目は、表面的には「変化が少ない」ように見えて、
内側では着実に前進していた1年でした。
私は「息子を変えよう」とするのをやめ、「自分ができること」に目を向け、
パートを始めることで親子の距離に変化が生まれました。
そして息子もまた、自分のタイミングで「フリースクールに行ってみたい」と言い出し、
苦手だった勉強にも少しずつ取り組み、テストや面接を受けることができました。
卒業式は出席しなかったけれど、
心から信頼できる先生たちが祝ってくれた、
かけがえのない「わが家なりの卒業式」も経験できました。
「不登校=失敗」ではありません。
その子にとっての“羽ばたける形”が、きっとどこかにある。
そう信じて、今日も私たちは歩んでいます。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ではまた!とらすけでした🐯
↓【不登校経験談】過去記事はコチラ↓
我が家の不登校経験談①~不登校になるまで~
我が家の不登校経験談②〜不登校の原因となった担任からの叱責〜
我が家の不登校経験談③〜スクールカウンセラー〜
我が家の不登校経験談④〜不安と焦り〜
我が家の不登校経験談⑤〜先生が変われば…期待と現実〜
我が家の不登校経験談⑥〜「生きているのがつらい」息子から届いたSOS
我が家の不登校経験談⑦〜母子ともに限界だった2学期の始まり〜
我が家の不登校経験談⑧〜発達検査でADHDが判明〜
我が家の不登校経験談⑨〜ADHD診断後に療育が見つからない!高学年・不登校のリアル〜
我が家の不登校経験談⑩〜通院をやめても、少しずつ前に進んでいた〜
我が家の不登校経験談⑪〜「学校以外の道」を探し始めた日々〜
我が家の不登校経験談⑫〜発達外来での絶望と、ペアレント・トレーニングという選択〜
我が家の不登校経験談⑬〜不登校2年目のリアル、ゲーム・昼夜逆転・親の葛藤〜
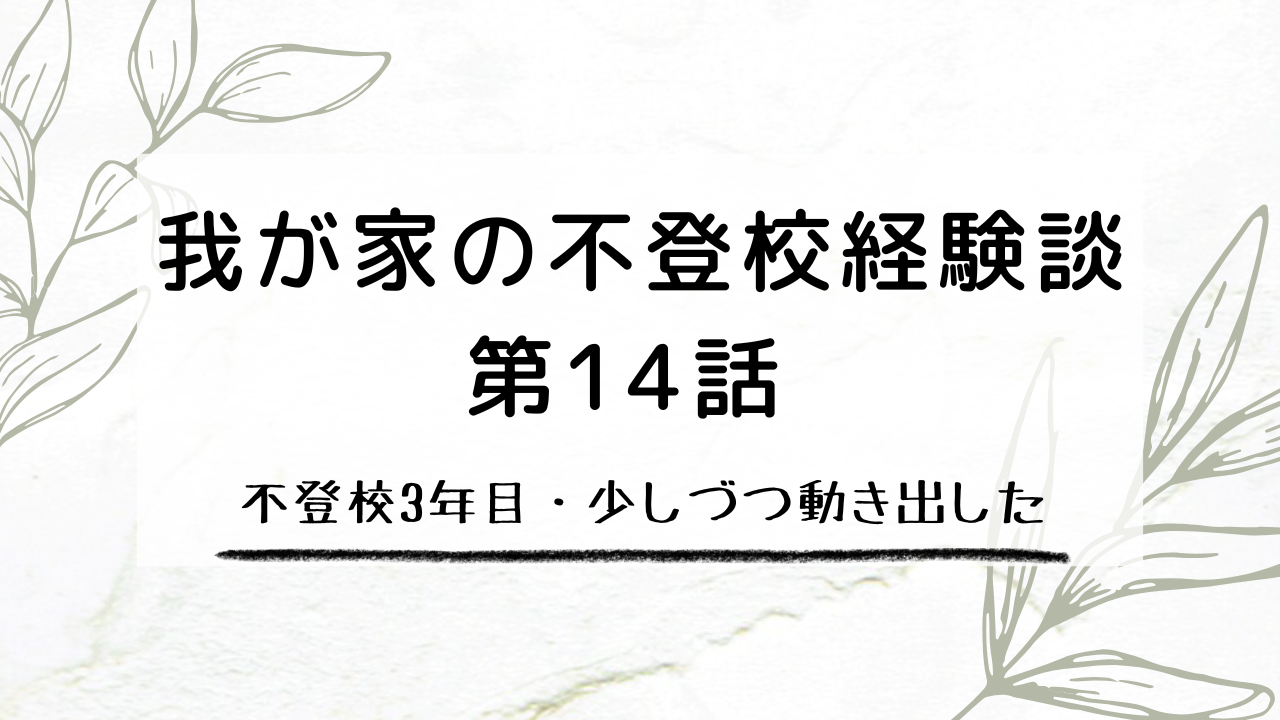

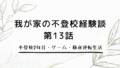
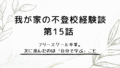
コメント