こんにちは。とらすけです🐯
»プロフィールはこちら
息子は小4で学校へ行けなくなり、小6まで完全不登校。
中1では希望のフリースクールに週1回通学、1年間継続しました。
そして現在中2。
自分の力で勉強をしたいと、フリースクールから新たな道へ切り替え中です。
小学校後半はほぼゼロ勉でしたが、今は自ら勉強をするまでに回復しました。
▼勉強に関する過去記事はコチラ▼
「【不登校】「勉強の遅れ」はどうする?不登校の子が勉強に取り組むために必要なこと」
前回の記事では、「夏休みの終わり〜2学期の始まり」について書きました。
2学期が始まってからも、うつ症状、パニック症状は続いていました。
今回は、「メンタルクリニックを受診」した時のことを書いていきたいと思います。
「メンタルクリニックへ行けば、うつ症状も改善し、
不登校対応のアドバイスもらえるだろう。」
そう思って病院へ向かったした私でしたが、
そこで言われたのは、
「発達検査をしてみませんか?」の言葉でした。
これをきっかけに、その後、想定外の展開となっていくのです。
今回も、不登校で悩んでいる方の参考になったら嬉しいです。
↓【不登校経験談】過去記事はコチラ↓
我が家の不登校経験談①~不登校になるまで~
我が家の不登校経験談②〜不登校の原因となった担任からの叱責〜
我が家の不登校経験談③〜スクールカウンセラー〜
我が家の不登校経験談④〜不安と焦り〜
我が家の不登校経験談⑤〜先生が変われば…期待と現実〜
我が家の不登校経験談⑥〜「生きているのがつらい」息子から届いたSOS
我が家の不登校経験談⑦〜母子ともに限界だった2学期の始まり〜
息子のパニック症状をきっかけに、児童精神科へ
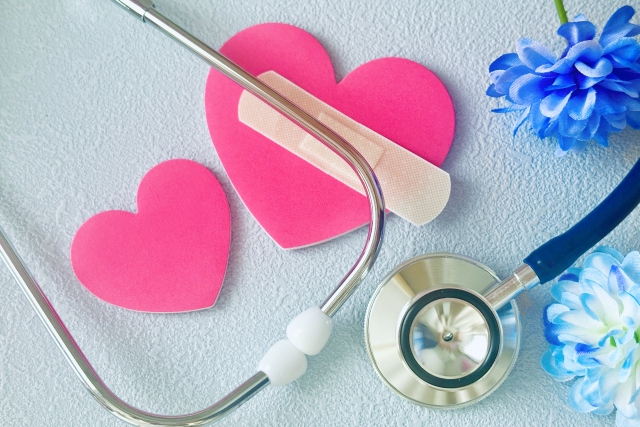
前回の記事で書いた、
息子が幻覚を見たり、パニックを起こしたことをきっかけに、
9月中旬、初めて児童精神科を受診しました。
病院を選んだ基準は?
最初は、不登校の対応に慣れてそうなクリニックを探していました。
しかし、不登校の子が増加している今、
不登校に特化していそうなクリニックは、
予約がまったく取れなかったり、新規受付を中止していたりで…
すぐに受診できるクリニックは見つかりませんでした。
最終的には、
・家から通いやすい
・児童が対象に入っている
・ホームページに不登校について書いている
・病院の雰囲気が安心できそう
・比較的早めに予約が取れる
という条件を満たした病院に決めました。
診察を終えて、先生からの提案
初診時には、
息子が生まれてからこれまでの成長を詳しく書いた問診票と、
小学校の通知表を提出しました。
診察は、親子そろって診察室に入り、先生と1対2で話すスタイル。
当時はまだコロナの影響が強く、
椅子は先生と十分な距離をとって配置されており、
その距離感のせいか、少し話しづらさを感じました。
また、心理士さんなどとの面談はなく、
診察は終始、先生からの質問に淡々と答えていくような流れでした。
具体的な不登校対応は教えてもらえませんでしたが、
・気持ちを和らげる漢方を処方
・学校は無理せず休ませてOK
まずはそれで、様子を見ましょうと。
そして最後に私だけ診察室へ呼ばれ、
先生から、このような提案をされました。
「ADHDの可能性があるかもしれません。発達検査を受けてみませんか?」
予想していなかった展開へ

息子は、この翌月に発達検査を受け、ADHDと診断されました。
実はずっと感じていた違和感
私は、以前からずっと、息子の行動に対して
・どうしてこんな簡単なことができないんだろう
・どうして一つ一つ順を追って行動できないんだろう
と、思っていました。
日々の生活の中で、自分と息子の感覚が、
あまりにかけ離れていることが多く、
ついイライラしてしまう日々が続いていました。
そして心の中では、ずっと疑っていました。
「たぶんADHDな気がする。」と。
でも、周りのママたちに相談しても…
・「男の子なんてそんなもんだよ〜」
・「うちの子もしょっちゅう忘れ物するし〜」
と言われてしまい、
「検査を受けたいけど、神経質な母親って思われるかも…」と、
発達検査を受けに行く勇気を出せずにいました。
「やっと検査が受けられる!」という安心感
そんな中で先生から「検査をしてみませんか?」と提案され、
「やっと受けられる!」と、とても安心したのを覚えています。
ショックは全くなく、「ようやくここまで来た」という気持ちでした。
診断を受けて感じたこと
ADHDと診断された時も、ショックは全くありませんでした。
むしろ、
・「やっぱりそうだったんだ」
・「私の育て方のせいじゃなかったんだ」
・「息子のせいでもなかったんだ」
という安心感のほうが大きかったです。
私がこれまで「どうしてできないの?」と責めてきたことは、
本人が怠けていたわけでも、努力不足だったわけでもなく、
頑張ってもできなかったんだ!息子も苦しかったんだ!
と知ることができたのです。
ようやく、息子の「苦手さ」を受け入れてあげることができました。
息子をより理解してあげられるようになった
先生は検査結果をもとに、次のようなことを説明してくれました。
・「ADHD」と言っても、子どもによって特徴や得意・不得意は異なる
・同じことをやっていても、他の子よりもエネルギーをたくさん使う
・エネルギーを使う分疲れやすく、しっかり休ませることが必要
・周りから理解されず、注意・叱責されることが増える
・何とか頑張らなければと頑張りすぎてしまう(過剰適応)
検査結果にも、息子の特徴がはっきりと出ていました。
先生の話にも、検査結果にも、納得することばかり。
この検査結果のおかげで、息子のことをより深く理解してあげられるようになりました。
もっと早くに受けていたら…という後悔

一方で、こんなことも思っていました。
・「もっと早く検査を受けていたら…」
・「息子のことをあんなに責めなくて済んだかもしれない」
・「息子の苦しい気持ちをもっと理解してあげられたのに…」
後悔の気持ちでいっぱいになりました。
でも、いくら後悔しても過去は変えられません。
これまでのことを反省して、今できること・これからできることを探していこう。
そう思うことにしました。
じゃあ具体的に、これからどうしていけばいいの?
ここから、
【「不登校」だけでなく「ADHDの特性」と、どう向き合っていくか】
を模索する旅が始まりました。
まとめ
「不登校」というだけでも手探りの日々だったのに、
思いがけず「発達特性(ADHD)」という新たな側面と向き合うことになった我が家。
でも検査を受けたことで、
ようやく息子の“生きづらさ”の理由が見えてきました。
診断は「ゴール」ではなく、「理解とサポートのスタート地点」。
この日をきっかけに、
「不登校」×「発達特性」という2つの視点から、
息子にとって心地よい日々を一緒に作っていく旅が始まりました。
同じように悩んでいる方にとって、少しでもヒントになれば嬉しいです🍀
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ではまた!とらすけでした🐯
↓【不登校経験談】過去記事はコチラ↓
我が家の不登校経験談①~不登校になるまで~
我が家の不登校経験談②〜不登校の原因となった担任からの叱責〜
我が家の不登校経験談③〜スクールカウンセラー〜
我が家の不登校経験談④〜不安と焦り〜
我が家の不登校経験談⑤〜先生が変われば…期待と現実〜
我が家の不登校経験談⑥〜「生きているのがつらい」息子から届いたSOS
我が家の不登校経験談⑦〜母子ともに限界だった2学期の始まり〜
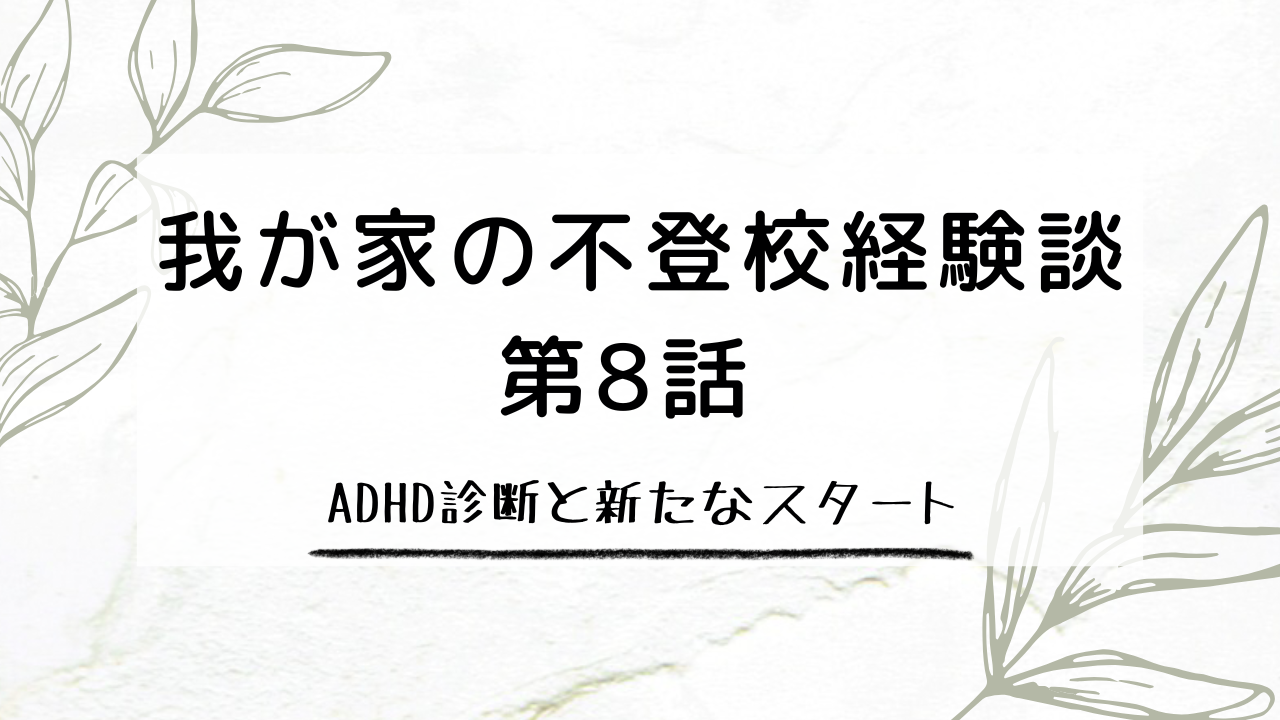

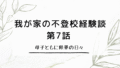
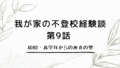
コメント