こんにちは。とらすけです🐯
»プロフィールはこちら
息子は小4で学校へ行けなくなり、小6まで完全不登校。
中1では希望のフリースクールに週1回通学、1年間継続しました。
そして現在中2。
自分の力で勉強をしたいと、フリースクールから新たな道へ切り替え中です。
小学校後半はほぼゼロ勉でしたが、今は自ら勉強をするまでに回復しました。
▼勉強に関する過去記事はコチラ▼
「【不登校】「勉強の遅れ」はどうする?不登校の子が勉強に取り組むために必要なこと」
ここまで書いてきた「経験談①〜⑫」は、不登校1年目の出来事でした。
(👇過去記事の一覧は下にまとめています👇)
まずは、ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
自分にとって最初の1年は、4年間の不登校生活の中で、1番濃く、1番長く感じた1年でした。
その分、経験談も長くなってしまいましたが、ここからは、もう少しペースを上げて行きたいと思うので(笑)、もう少しお付き合いください。
今回は、不登校2年目に入ってからの記録をお届けします。
この時期になると、朝の「行く行かない」のやり取りもすっかりなくなり、不登校生活が定着・安定してきました。
でもそれはそれで、新たな悩みも出てきました。
・昼夜逆転
・ゲーム・YouTube漬け
・全く勉強しない
・歯みがきをしない
・薬を飲まない
・髪を切りたがらない
などなど…
不登校で悩む保護者さんの多くが通る道ではないでしょうか。
今回は、そんな状態だった息子と私の日々について、振り返っていきたいと思います。
今回も、悩んでいる誰かの参考になったら嬉しいです。
↓【不登校経験談】過去記事はコチラ↓
我が家の不登校経験談①~不登校になるまで~
我が家の不登校経験談②〜不登校の原因となった担任からの叱責〜
我が家の不登校経験談③〜スクールカウンセラー〜
我が家の不登校経験談④〜不安と焦り〜
我が家の不登校経験談⑤〜先生が変われば…期待と現実〜
我が家の不登校経験談⑥〜「生きているのがつらい」息子から届いたSOS
我が家の不登校経験談⑦〜母子ともに限界だった2学期の始まり〜
我が家の不登校経験談⑧〜発達検査でADHDが判明〜
我が家の不登校経験談⑨〜ADHD診断後に療育が見つからない!高学年・不登校のリアル〜
我が家の不登校経験談⑩〜通院をやめても、少しずつ前に進んでいた〜
我が家の不登校経験談⑪〜「学校以外の道」を探し始めた日々〜
我が家の不登校経験談⑫〜発達外来での絶望と、ペアレント・トレーニングという選択〜
最後まで手放せなかった「せめて◯◯」とは?

長男が学校へ行けなくなってから1年が経ち、小5になりました。
この1年は、「せめて朝は起きてほしい」「せめて少しは勉強を」など、“せめて◯◯”という気持ちとの戦いの毎日でした。
そして、葛藤しながらも、その「せめて」を少しずつ手放していった1年でした。
でも…
最後まで手放せなかったのが「ゲームとYouTubeの時間制限」。
心のどこかで、「今の息子にとっては、これが唯一のできることなんだ」とわかっていました。
制限することで親子関係が悪くなる、精神的に不安定になるリスクも理解していました。
それでも、朝から晩まで、目の前でゲームばかりの息子…
ゲーム以外の活動を何もしない息子を見ることが、どうしても受け入れられませんでした。
ゲーム制限を手放せなかった本当の理由

もちろん、時間制限をしてうまくいく家庭もあると思います。
でも我が家の場合は、制限するのは逆効果なパターンでした。
私自身、当時の息子の状態では「本人の好きなようにさせる方がいい」と、うすうす感じていました。
あとは、【私自身の感情の問題】だったのです。
「どうして私はこんなに嫌なのか?」と問い続けて、出てきた答えは──
【私が】不安になるから
このままゲーム依存になって、一生引きこもったらどうしよう?
このまま大人になったらどうしよう?
そんな不安に、【私自身が】耐えられなかったのです。
ゲームとYouTubeを止めさせたいと思っていたのは、本人の問題ではなく、私の問題だったと気づきました。
息子にとって、ゲームは“心を守る盾”だった

でも一方で…
不登校の子どもたちは、「ゲームやYouTubeで自分の心を守っているんだろうな」とも感じていました。
これを取り上げるということは、「今の息子が唯一持っている“心の盾”を奪うこと」。
これまでの1年を振り返り、原点となったあの夏休みに立ち戻り…
ここまでの息子の変化を改めて思い出してみる。
そこでもう一度、
「時間制限をして親子でバトるのか」
or
「今はゲームが息子の心を守ってくれていると割り切って、息子を信じるのか」
“自分たち親子にとってどちらがプラスになるのか”と考えてみる。
そんな葛藤を、何度も何度も繰り返しました。
そうしているうちに、徐々に自分の執着を手放していけるようになりました。
「不安」を捨てろ!と言われても無理だと思います。
私も今でもたくさん不安はあります。
その不安はお母さんたちの大切な感情です。
否定しなくてもいいと思うんです。
「ああ、私はここが不安なんだな…そうだよね、不安になって当たり前だよね…」とヨシヨシしてあげてほしいです。
ただ一方で、
【親の不安】と【子どもの気持ち】は、別物です。
私はこの頃から、自分の感情と息子の感情の間に「境界線を引く」という感覚が、何となくわかり始めたような気がします。
オンラインフリースクールで息子に変化が

オンラインフリースクールに入ってみた
そんな時、たまたま参加した不登校支援のセミナーで「オンラインフリースクール」を紹介されました。
「息子くんのようなタイプの子にはここが合うかもしれないですね。」と言われ、息子に軽く話してみたところ、「やってみたい!」と。
ちょうどその頃、自分用のパソコンを購入したばかり。これがフリースクール参加への後押しとなり、私たちは思い切って入会を決めました。
ゲームと仲間が息子の心を癒やした
そのフリースクールは、時間割もなく、オンラインで子ども同士がつながって自由に過ごすスタイル。息子のようにゲーム好きな子たちも多く、自然と友達ができていきました。
一見「ゲームさせるために入れるの?」と思われるかもしれませんが、心が疲れきった子どもにとって、無理をせずに友達と楽しく遊べることは“心のエネルギー回復”に繋がることもあります。
当時の息子には、まさにぴったりの環境でした。
そして驚いたことに、1年間ずっと曇った表情をしていた息子が、毎日本当に楽しそうな笑顔を見せてくれるようになったのです。
昼夜逆転は“心の充電期間”だった
もちろんその代償(?)として、ゲーム時間は増え、夜遅くまでプレイしてしまうようになりました。完全な昼夜逆転まではいかないまでも、小5にしては昼夜逆転気味の生活。
でもうちの息子の場合は、フリースクールに入らなくても、いずれ通った道だと思いました。
我が家の場合は、時間制限を厳しくすればするほど、私に対する信頼感がさらに減っていく感覚がありました。
回復のプロセスとして、“ゲーム漬け・昼夜逆転・生活リズムの乱れ”の期間を過ごすことは、仕方のないことだと、思うようになっていったのです。
家の外にも興味が出てきた息子

小5の4月にフリースクールに入会し、【家の中では】笑顔も増え、元気になってきた息子。
それから半年ほど経った、小5の2学期ごろ。
家の【外での活動】への興味が芽生えました。
「ロードバイクに乗って、サイクリングをしてみたい!」と言い始めたのです。
ただ予想通り、「ロードバイクを買って欲しい。」が始まりました。
でも、ロードバイクはそう簡単に買えるお値段ではない。
ましてや、これからどんどん身長が伸びる成長期。
買っても、すぐに小さくなってしまう…そんな簡単に買い換えられるものではありません。
一旦は荒れることを覚悟で、現実的には買うのは難しいことを、理由と共に説明しました。
蘇る、1年前の出来事の数々…。
でも、あれから1年経って、息子も成長していました。
最初は荒れはしたものの、時間が経って冷静になると、少しずつ理解してくれました。
この時、気をつけていたこと。
・息子の気持ち自体は否定しない。
・買ってもらえず悲しい気持ちも否定せず、共感的に受け止める。
・全ては叶えられないが、叶えられる範囲のことは全力で応援・協力することを提案。
高いロードバイクは変えないけれど、それまで乗っていた子供用のマウンテンバイクから、中学生くらいまで乗れるかっこいいデザインの軽い自転車に買い替えることを提案。
そして、週末になる度に、息子が行ってみたい目的地まで、息子自身が選んだコースでサイクリングをするようにしました。
距離はどんどん伸び、最後には、何十キロも離れた目的地まで泊りがけで行くところまで達成していました。
ロードバイクならもう少し楽に越えられる峠を、軽いとは言え普通の自転車で越える…
なかなかハードだったと思いますが、それも笑い話に変えるほど頼もしい息子に成長していました。
帰宅した息子の笑顔は、とてもイキイキしていました。
アラフォーの体に鞭打って、息子に付き合った旦那には、感謝の気持ちでいっぱいです。
(でも普段何の運動もしてないし、運動不足解消ということで、いいよね!?)
その後は、ある程度やり切り満足したのか、サイクリングへの熱は次第に覚めていきましたが、今でも年に一度、ロードバイクをレンタルし、父子2人で泊りがけサイクリングに行くのが恒例になっています。
まだまだ苦しい時期ではあったけれど、不登校にならなければチャレンジしなかったと思うし、息子のイキイキした笑顔の貴重さにも気付けなかったかもしれません。
ついに…「勉強してみようかな」と言い出した

またその頃、息子が「ちょっと勉強してみようかな…」と言い始めました。
でも、その頃はまだなんとなく、「罪悪感」や「義務感」から言っているようにも感じました。
本人のチャレンジをサポートしつつも、まだ本格的な勉強に耐えられる状態ではないなと。
でも、やりたいと思っただけで大きな一歩。
「やっぱりだめだった」のパターンも想定しつつ、家庭教師の体験をしてみることに。
先生にはこれまでの経緯や今の精神的な状態も伝え、勉強というよりも、雑談中心の授業をお願いしました。
そしたら、「こんな感じならできそう!」と息子。
ただし金銭的にフリースクールと両立は難しく、家庭教師かフリースクールのどちらかを選ぶ必要があることを説明しました。
実はその頃、フリースクールで仲の良かった友達と喧嘩をしてしまったタイミングでした。
結局はスタッフさんのサポートもあり、仲直りしたのですが、息子の中で「オンラインフリースクール」がどういうものか体験し、「同じ境遇の友達とのつながり」もできて、フリースクールに在籍すること自体はそこまで重要ではなくなっていたタイミングでした。
ちょうど本人の中で一区切りついて、次のステップについて考えるタイミングだったのだと思います。
息子は自ら「フリースクールはやめて、家庭教師にする」と決断しました。
(しかしこのまま順調に勉強できるようにはなりませんでした。そのことについては、また別記事で…)
ちなみに、フリースクール退会後も、その友達グループとはオンラインで交流を続けていました。
“否定しない・普通に接する”を続けた結果

1年以上経っても、私の感情はついていかないこともたくさんありました。
でも、
・どんな姿でも否定しない
・学校へ行ってる子と同じように接する
・学校や勉強に関係ない話でも、本人の話したいことを聴く
これらを意識しながら過ごすうちに、息子は少しずつ元気になっていきました。
「そうは言ってもそれが難しいから悩んでるんです!!」
そんな声が聞こえてきます。
わかります…
わかりますよ(涙)
でもね…。
どうせ悩むなら、
ただ子どもとバトって過ごすよりも、
少しでもプラスになる対応を意識して過ごすほうがよくないですか?
すぐには変化は感じられないと思います。
でも、その意識をするかしないかで、何ヶ月後、何年後の親子関係はきっと違うものになっていると思うんです。
苦しい時は、ノートに感情を書き殴ってみるのもオススメです。
ノートなら誰にも聞かれないし、家に子どもがいても、スキマ時間で書けます!
「こんなこと書いたら…」とか思わずに、自分の感情をちゃんと見てあげて。
そして、「そうだよね。辛いよね。こんなに私頑張ってるのに!!うん、よく頑張ってる!よしよし!」って。自分の心も大事にしてあげて欲しいです。
今、本当に苦しいし、虚しくなることもたくさんあると思います。
「きっと大丈夫!」と言われても、信じられないと思います。
でも…
どうせ悩んで過ごすなら、ちょっとでもプラスになる意識を持って過ごしてみませんか?
まとめ
不登校2年目の我が家では、「ゲームばかりで何もしない息子」をどう受け止めるかという、また新たな葛藤が始まりました。
「制限しないとダメなんじゃないか」
「このままじゃ将来が不安」
──そんな思いに揺れながらも、少しずつ「親の不安」と「子どもの気持ち」は別物だと気づき、境界線を引けるようになっていきました。
オンラインフリースクールで笑顔が戻り、サイクリングや家庭教師など、新しい世界にも興味を持ち始めた息子。
それは、ゲームやYouTubeに夢中になる“充電期間”を経たからこそ、芽生えた変化だったと思います。
大切なのは、焦らず、否定せず、普通に接しながら、子どもが自ら動き出すまで信じて見守ること。
親だって不安になるのは当然だからこそ、自分の気持ちにも優しく寄り添いながら──。
今悩んでいるあなたにも、きっと大丈夫と思える日がきますように。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ではまた!とらすけでした🐯
↓【不登校経験談】過去記事はコチラ↓
我が家の不登校経験談①~不登校になるまで~
我が家の不登校経験談②〜不登校の原因となった担任からの叱責〜
我が家の不登校経験談③〜スクールカウンセラー〜
我が家の不登校経験談④〜不安と焦り〜
我が家の不登校経験談⑤〜先生が変われば…期待と現実〜
我が家の不登校経験談⑥〜「生きているのがつらい」息子から届いたSOS
我が家の不登校経験談⑦〜母子ともに限界だった2学期の始まり〜
我が家の不登校経験談⑧〜発達検査でADHDが判明〜
我が家の不登校経験談⑨〜ADHD診断後に療育が見つからない!高学年・不登校のリアル〜
我が家の不登校経験談⑩〜通院をやめても、少しずつ前に進んでいた〜
我が家の不登校経験談⑪〜「学校以外の道」を探し始めた日々〜
我が家の不登校経験談⑫〜発達外来での絶望と、ペアレント・トレーニングという選択〜
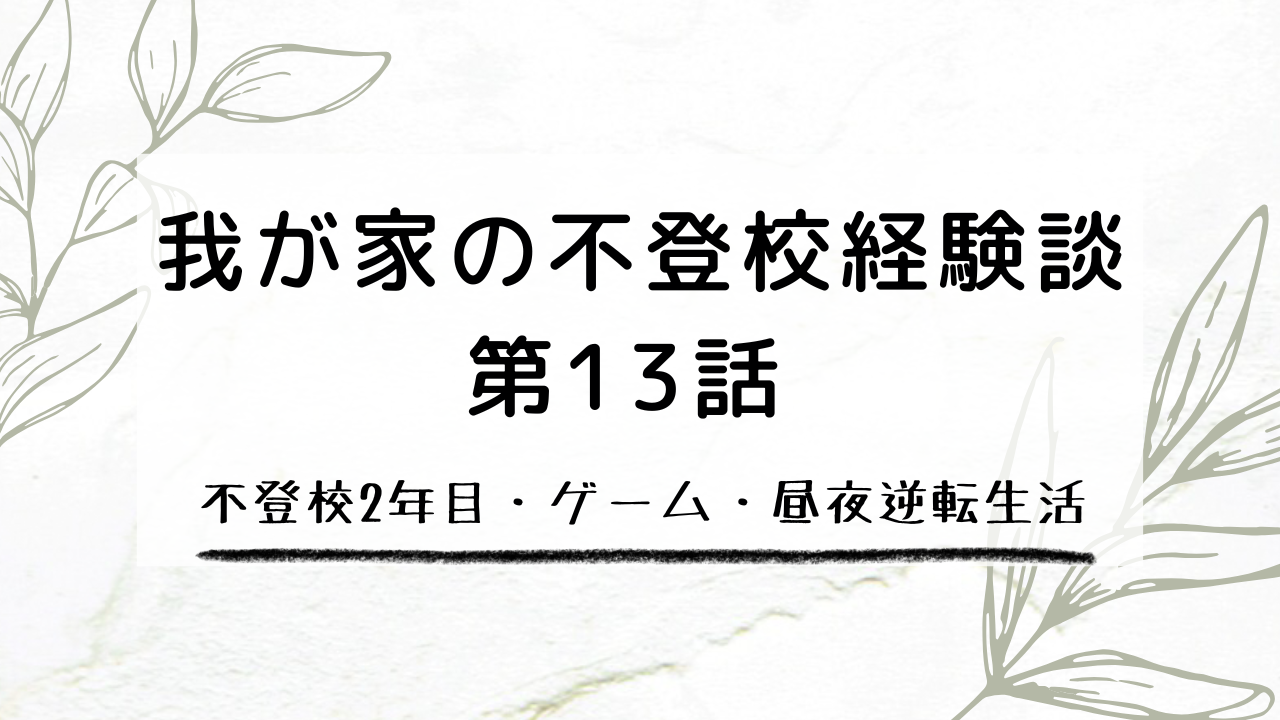

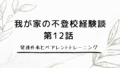
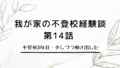
コメント