息子は小4で学校へ行けなくなり、小6まで完全不登校。
中1では希望のフリースクールに週1回通学、1年間継続しました。
そして現在中2。
自分の力で勉強をしたいと、フリースクールから新たな道へ切り替え中です。
小学校後半はほぼゼロ勉でしたが、今は自ら勉強をするまでに回復しました。
▼勉強に関する過去記事はコチラ▼
「【不登校】「勉強の遅れ」はどうする?不登校の子が勉強に取り組むために必要なこと」
前回は、いよいよ連続で休みが続いた時の経験談を書きました。
今回は、連続で数日休んだ後の親子の葛藤について書いていきたいと思います。
ずっと休むようになったらどうしよう

前回の経験談で書いた通り、5月後半に担任からひどい叱責を受けたことがきっかけとなり、息子は5月末から連続で休み始めました。
6月初めにはスクールカウンセラーに相談しましたが、逆に息子の学校不信が強まってしまい、翌日も学校へ行けず、ついに4日連続で欠席しました。
それでも当時の息子は、「学校に行かなきゃ」という気持ちと葛藤していました。
私もまた、「どうしたら行けるようになるんだろう」と、「行かない息子」を受け入れることができませんでした。
「今は休ませたほうがいい」と頭では理解していました。
でもそれは「ずっと休む」ではなく、あくまでも「今だけ」。
心の中では常に「このままずっと行けなくなったらどうしよう」という不安がありました。
なので私はその「自分の不安」を解消するため、息子の「学校へ行きたくない理由」を聞き出しては、一つ一つ解決しようと必死になっていました。
今でこそ「子どもの話を聴いてあげることが大事」と言える私ですが、当時はそんなふうに広い心ではいられませんでした。
今後は、私の「暗黒毒母時代」の話が出てきますが、これが不登校に向き合う親子のリアルな葛藤なのだと思って読んでいただけたら嬉しいです。
実は、原因となった担任は…

ここで少し、担任の話を挟みます。
実はその担任、もともと6月後半に産休に入る予定でした。
そう、妊娠中だったのです。
出産経験のある一人の人間として、妊娠中の大変さは分かっているつもりです。
妊娠中にも関わらず教員という大変な仕事をしていたこと自体は、本当にすごいと思っています。
ただこの担任は、妊娠前から叱責が強いタイプだったことも、上級生の保護者から聞いていました。
なので「妊娠しているから仕方ない」という気持ちとは、切り離して考えています。
そのような流れもあり、6月頭に連続して休みはしたものの、
「あと少し我慢すれば担任が変わる。きっとそしたらまた行けるようになる!」
と期待していました。
苦しかった6月の登校

心配と焦り
6月のはじめに連続欠席したものの、その時点では息子も私も、「学校へ行くこと」を目標にしていました。
当時息子は、「学校に行きたいと思っているけど、朝になると頭痛がひどくなってどうしても行けない。」と言っていました。
ただ、息子の「行きたい」は本当の意味での本心ではなかったのだと思います。
本当は限界だったのに、
「お母さんが不機嫌になるから」
「友達に何か言われるかもしれないから」
「学校は行かないといけない所だから」と、無理をしていました。
今思うと、息子の「行きたい」は本当に心から「学校が楽しみで行きたい」ではなく、心と体は限界だと悲鳴を上げているけど、「(行かなきゃいけない所だから)行けるようになりたい」だったのかなと。
実際私は、毎朝息子が「頭が痛い」と言い出した途端、機嫌が悪くなっていました。
口では、
「無理しなくていいよ。辛いよね。」
「あまりに辛ければ休んでいいよ。」と言いながらも、
心の中では
「これ以上休んだら、このまま行けなくなるかもしれない。」
「自分の予定がまた狂ってしまう。」
そんな焦りでいっぱいでした。
心の中で思っていることが、すべて私の表情、態度に現れていました。
息子はきっと、私のそんな空気を敏感に感じ取っていたと思います。
月曜日は特に頭痛がひどく、休むこともありましたが、少しでも体調がマシな日は励ましながら送り出していました。
友達が迎えに来てくれる日もあり、6月は休みながらも何とか登校できていました。
カウンセラーや担任からも
「学校に来れば元気にしていますよ!」
「遅刻でもいい、少しでもいいから顔を出しましょう。」 と言われました。
結局私は、学校に不信感を抱きつつも「このまま不登校になったらどうしよう」という焦りから、「息子を学校へ行かせること」で自分の不安を解消してもらおうとしていたのです。
こうして私は「登校するかしないか」ばかりに目を向け、息子の心のエネルギーがさらにすり減っていることに気づけていませんでした。
大事なのは言葉の奥に隠れた本当の気持ちだった

最初から「学校が辛いなら休めば良い!」と思っている子はいないと思います。
子どもたちは、「学校に行くのが当たり前」と教わって育っています。
それに加えて、母のイライラした態度。
だから限界ギリギリでも、「頑張らなきゃ」と自分を追い込んでしまうんですよね。
ただ、本人が「学校行きたくない」と口にするのは、ずっとずっと我慢を重ねた末に出てくる言葉。
大人からすると、「学校に行きたくない」と言われた時がスタートに見えるけれど、
子どもたちにとっては、そこに至るまでに限界ギリギリまで頑張った道のりがあるんですよね。
この感覚のズレが、子どもを苦しめ、大人も不安にさせてしまうのだと思います。
「学校に行ってしまえば元気に過ごしている。」
たぶんこれ、うちだけじゃないと思うんです。
先生からそう言われたことのあるお母さんたち、多いんじゃないかなーと。
息子も、「頭は痛かったけど、友達に会ったら元気になった」と言っていたので、
その瞬間瞬間では元気を取り戻していたのかもしれません。
でも、朝になると頭痛がひどくなり、登校を渋る。
表面上は学校で楽しく過ごしているように見えても、結局、心のエネルギーは枯渇状態なんです。
本当に必要だったのは、「とにかく登校すること」ではなく、本当の気持ちを聴いてそれを受け入れてあげること。
どんなに大人が不安になる内容でも一般的な正解からズレていても、今の子どもの本心を否定せずに受け止めてあげる。
それにより心のエネルギーを回復させてあげることだったのだと、今は思います。
叱責事件を知る
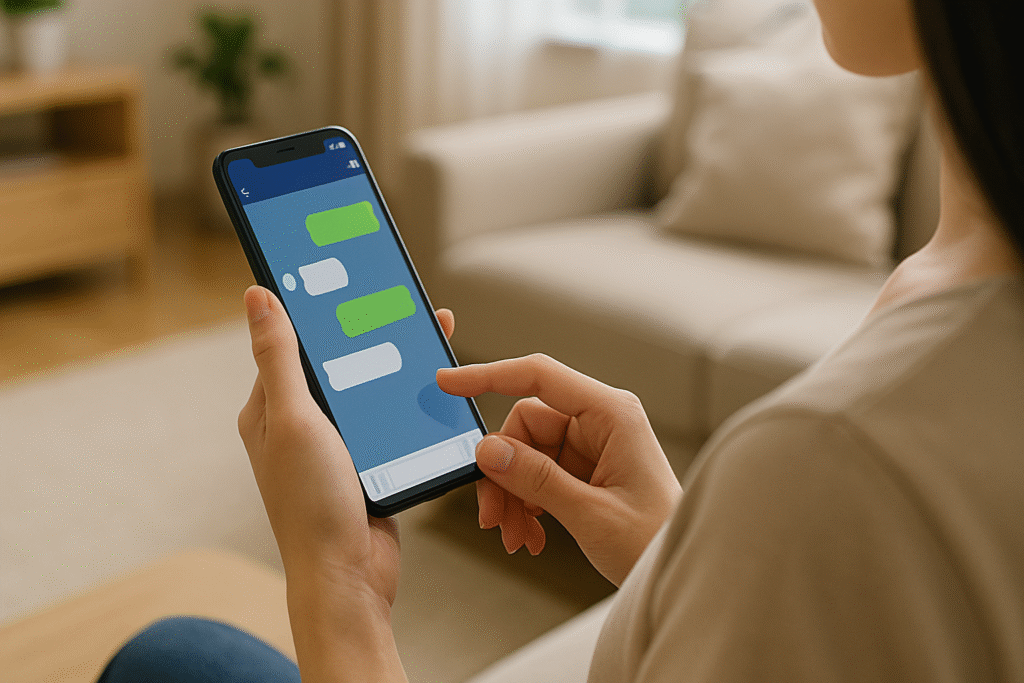
一方で、息子が休みがちになってしばらく経ったある日。
友達のお母さんから連絡がありました。
お子さんが、息子の叱責事件のことを話してくれたというのです。
私はその時、初めて事件の詳細を知りました。
思い返せば、息子の様子がおかしくなったのもその頃。すべて辻褄が合いました。
担任が産休に入る直前、個人面談がありました。
本当は、そのタイミングで担任に事実確認ができればよかったのですが、
息子本人は何も話してくれず、証拠もない。
しかも、もうすぐ出産を控えた妊婦さんに強く言うことにも抵抗があり…
結局、個人面談でも聞き出すことができませんでした。
今となれば、「あの時、遠慮せず言えばよかった」と思いますが、その時の私は、「学校に悪く思われたくない」「良い母だと思われたい」など、我が子の心よりも世間体を優先してしまっている人間でした。
個人面談では深い話にはならず、担任は何事もなかったかのように学校を去っていきました。
まとめ
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
不登校初期の葛藤は特にに苦しいです。
親も子も心の中で不安や焦りを感じながら、必死に向き合っておられると思います。
でも、どんなに辛い時でも、親も子も決して悪くないんです。
私たちは、「学校に行けなくなった」という現実に向き合い、少しでも前に進もうとしています。
その中で、親が不安や焦りを感じることは自然なこと。
でも大切なのは、子どもの本当の気持ちに耳を傾けること。
どんなに焦っても、「無理に登校させること」は解決にはならないことを、身を持って学びました。
不登校は終わりではなく、新たなスタートです!
親も子も一緒に成長していくチャンスです。
これからも心のエネルギーを大切にしながら、少しずつ進んでいけたらいいなと思っています。
これからも、不登校に向き合う親子のリアルな葛藤をお伝えしていきますので、また読みに来てもらえたら嬉しいです。
とらすけでした🐯
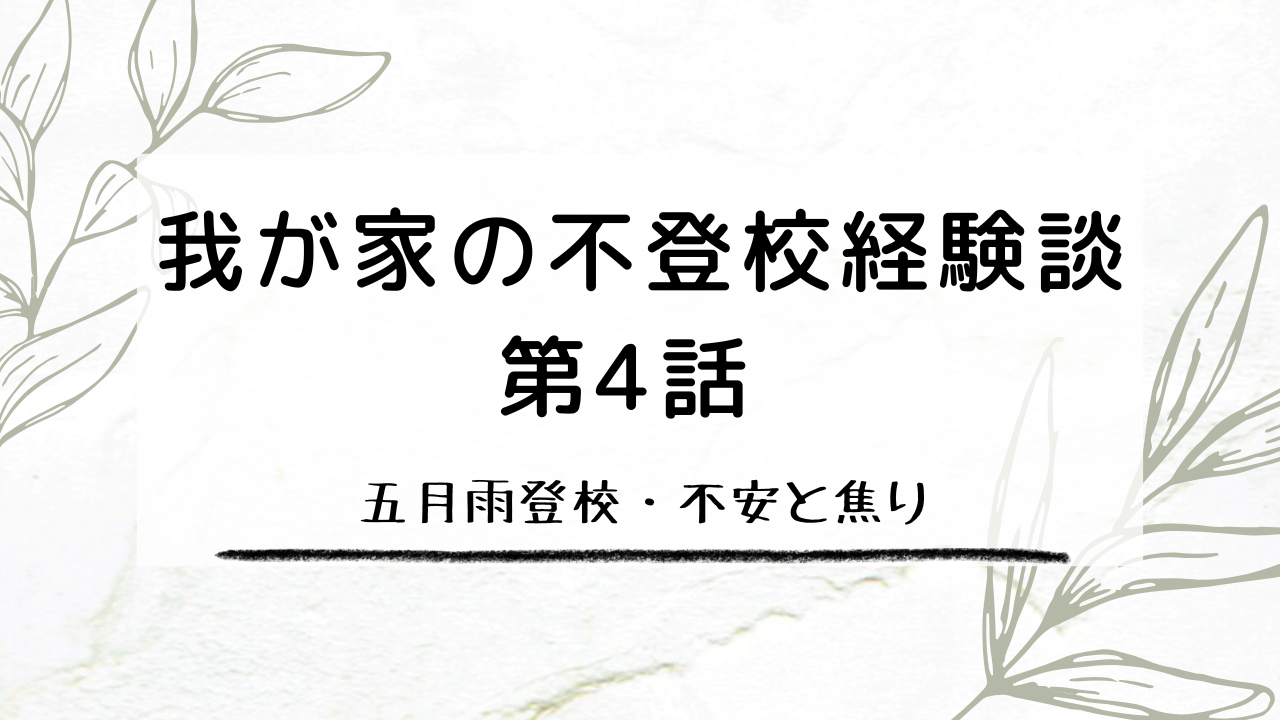

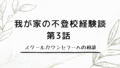
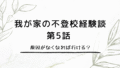
コメント