こんにちは。とらすけです🐯
»プロフィールはこちら
息子は小4で学校へ行けなくなり、小6まで完全不登校。
中1では希望のフリースクールに週1回通学、1年間継続しました。
そして現在中2。
自分の力で勉強をしたいと、フリースクールから新たな道へ切り替え中です。
小学校後半はほぼゼロ勉でしたが、今は自ら勉強をするまでに回復しました。
▼勉強に関する過去記事はコチラ▼
「【不登校】「勉強の遅れ」はどうする?不登校の子が勉強に取り組むために必要なこと」
不登校を機に、発達検査でADHDと診断された息子。
経験談 第9話では、検査結果を受け、療育機関を探したときのお話をしました。
今回はその続きを書いていこうと思います。
第9話で、やっとたどり着いた【療育が受けられる発達外来クリニック】。
初診を待つこと数ヶ月。
・待ちに待った発達外来での出来事
・そして最終的に行き着いた「ペアレント・トレーニング」
について、経験談を書いていこうと思います。
今回も、悩んでいる誰かの参考になったら嬉しいです。
↓【不登校経験談】過去記事はコチラ↓
我が家の不登校経験談①~不登校になるまで~
我が家の不登校経験談②〜不登校の原因となった担任からの叱責〜
我が家の不登校経験談③〜スクールカウンセラー〜
我が家の不登校経験談④〜不安と焦り〜
我が家の不登校経験談⑤〜先生が変われば…期待と現実〜
我が家の不登校経験談⑥〜「生きているのがつらい」息子から届いたSOS
我が家の不登校経験談⑦〜母子ともに限界だった2学期の始まり〜
我が家の不登校経験談⑧〜発達検査でADHDが判明〜
我が家の不登校経験談⑨〜ADHD診断後に療育が見つからない!高学年・不登校のリアル〜
我が家の不登校経験談⑩〜通院をやめても、少しずつ前に進んでいた〜
我が家の不登校経験談⑪〜「学校以外の道」を探し始めた日々〜
やっと来た!待ちに待った発達外来の初診日

数ヶ月前に予約をしてから、ずっと待っていた発達外来の初診日。
「これで、やっと前に進める!」そう期待してその日を迎えました。
期待していた受診…でも行けなかった息子
病院からは「必ず本人が来てください」と言われており、もちろん息子にも伝え済み。
当日も、何度も「もうすぐだよ」「○時に出発だよ」と声をかけて、準備していました。
でも…
いざ出発の時間が近づくと、「行きたくない」と言い出す息子。
頑張って説得しようとするも、最後には布団にもぐって泣き出してしまったのです。
この頃の息子は、病院に限らず、外に出ること自体にかなり抵抗を示していました。
家族でのレジャーですら、直前で「やっぱり行けない」となることも。
なので想定はしていたのですが、いざ行かないとなると…
「やっと療育が受けられるかもしれないのに…。やっと前に進めそうなのに…。」
私は、がっかりした気持ちでいっぱいになりました。
でも、どうにもならず…
仕方なく、病院に電話をして、事情を説明しました。
本人不在でもOKに
電話をした時点で、もう出発しないと予約時間に間に合わないタイミングでした。
「本当は本人が来なければ診察はできない決まりですが…。今回は検査結果や紹介状もありますし、特別にお母さんだけで来てください。」
そう言っていただき、その日は、私だけで病院へ向かうことになりました。
診察室へ

担当医に感じた違和感
診察室に入ってみると、担当は年配のおばあちゃん先生。
言葉ではうまく説明できないけど、合った瞬間のその先生から感じる雰囲気に、
正直、「あれ…思ってた雰囲気と何か違うな…」と、違和感を感じました。
でも、ここは発達外来の専門クリニック。
患者さんの数も多いし、先生も複数いるほどの専門クリニック。
「経験もあるだろうし、大丈夫なはず」と、自分に言い聞かせて椅子に座りました。
前のクリニックで受けた検査の結果や、現在の息子の状況を説明すると、
「次回は息子くんも一緒に来てね。来られるようなら、いくつか検査もしてみましょう。」と。
最初に違和感を感じたものの、その日は、やわらかい口調でそんな風に言ってくれた記憶があります。
心理カウンセリングの提案、しかし…
本人不在ということもあり、初診では深い話まではできませんでした。
でも、「心理カウンセリングを受けてみてもいいかも。」と提案されました。
私としては、前の児童精神科でもカウンセリングを期待して受診していたところもあったので、「ぜひ!」という気持ちで、診察後に受付で予約をお願いしました。
でも…返ってきた回答は、
「今ご案内できるのは、最短で5ヶ月後になります。」
え、5ヶ月後!?
初診だけでも数ヶ月待ったのに!?
ここから心理カウンセリングを受けるのに、さらに5ヶ月待たないと行けないの!?と、途方にくれました。
でも、今さら他の病院を探して初診から…というのは現実的ではなく、5ヶ月待つことに決めました。
ちなみに、担当医の次の診察は3ヶ月後と言われました。
通常診察の再診でも3ヶ月待ち…これもなかなかの衝撃でした。
ついに3ヶ月後の再診…でも息子にとって辛すぎる診察だった
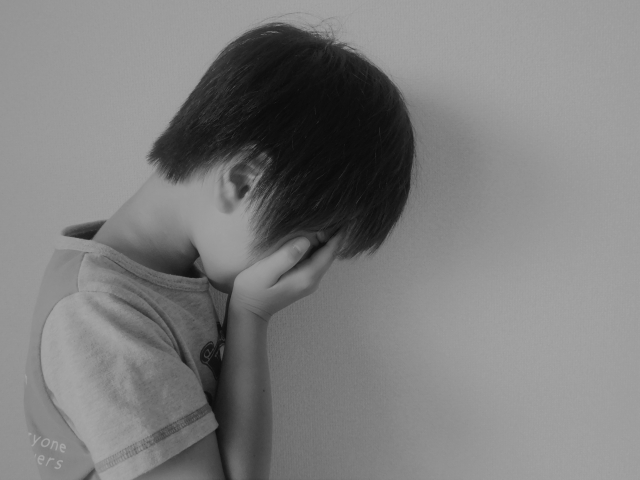
今度こそ!絶対に連れていかなきゃ!
そして迎えた、3ヶ月後の再診日。
今回は何とか息子を連れていかなければ、診察してもらえません。
「今回こそは行こう」
「大丈夫、先生に相談できるチャンスだから」
「先生も、優しい先生だったよ」
と前向きな言葉をかけ、何とか説得しました。
息子も渋りながらも、頑張って病院に向かってくれました。
ところが…診察室で言われたのは医師からの心ない言葉
3ヶ月ぶりの担当医による診察。
今回は本人が来院できたので、診察前に簡単な発達検査(?)がありました。
アンケート形式のものに丸をつけていったり、絵を描いたり。
そして検査結果についての説明を受けました。
しかし…
その後に医師が息子にかけた言葉が、あまりにもひどい内容だったのです。
内容の詳細を書くと長くなってしまうので、また別記事で書こうと思いますが、
不登校でうつ症状まで出ている子どもを、より追い詰める内容だったのです。
発達に悩む子どもたちやその親と向き合っている医師のはずなのに…
信じられませんでした。
息子は途中から涙を流し始め、もうその空間にいることが限界の状態に。
私もそばで聞いていて、信じられなさすぎて、しばらく言葉が出ませんでした。
それでも医師は話を続けようとしていたので、
耐えられなり、「もうそれ以上はやめてください(怒)」と止めました。
そして、診察が終わりました。
息子の「もう行きたくない」がすべてを物語っていた
待合室に戻ってきた息子は、こう言いました。
「もう、この病院には絶対来たくない!
この駅に来るのもイヤだ!!
他の病院も、もうどこにも行きたくない!!!」
この言葉が、すべてを物語っていました。
会計のときに受付の人から「次回のご予約は…」と聞かれましたが、予約はせずに帰宅しました。
5ヶ月後に予約していた心理カウンセリングも、キャンセルしました。
トレーニングの道が閉ざされた私たち。でも…
担当医の心ない対応で、私達親子の選択肢が、また1つ減ってしまいました。
「あの時、もっと早く止めていれば…」
そんな後悔もありました。
でも、あの先生がどういう人間なのか早めにわかっただけでも、よかったのかもしれない。
神様が「あなたたち親子にとって、そこは違うよ!」と教えてくれたのかも。
そう思うようにしました。
とはいえ、息子の困りごとが消えるわけではありません。
放っておいてよくなるものでもない。
診断を受けたことで、息子自身にもどうにもできない苦手さがあることは理解できた。
でも、困りごとがある限り、日常生活で私のイライラはきっと変わらない。
じゃあ…どうすればいいの?
行き着いたのは「ペアレント・トレーニング」
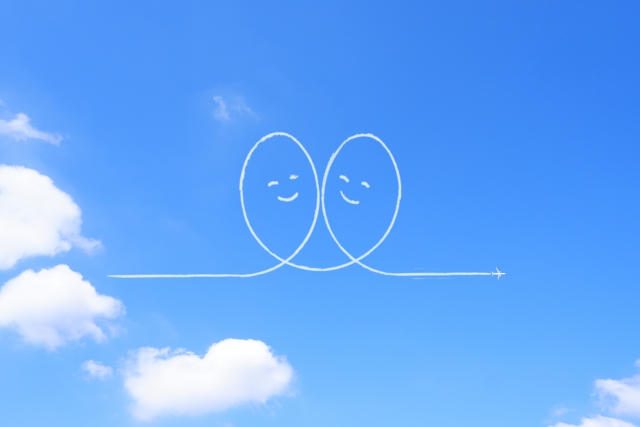
自分で学ぶしかない!
本人に療育を受けてもらう道は、完全に閉ざされた。
それなら…自分が学ぶしかない!
そうして行き着いたのが、「ペアレント・トレーニング」という選択でした。
情報を集めてみたけど…
ここでまた、ペアレント・トレーニングに関する情報を集め始めました。
知り合いの発達特性のある子のママに聞いたりして、講座の情報ももらいました。
しかし、ここでもまた「高学年以降」の壁がありました…
どの講座も、対象年齢が小さな子向けだったのです。
10歳の息子に、小さい子向けの内容をそのまま当てはめるのは、正直無理がありました。
ユーキャンの資格講座も受けてみた
ちょうどいいペアレント・トレーニングが見つからなかったので、まずはユーキャンで見つけた「発達障害児支援アドバイザー」という資格講座も受講してみました。
私は発達障害に対する知識があまりなかったので、すごく勉強になったし、発達障害についての基本を学ぶいい機会になりました。
でも、「目の前の息子の日常の困りごとに対し、具体的にどう対応していくか」という点では、相変わらず、どうしたら良いのかわからないままでした。
有料のペアレント・トレーニングを受ける決意をした

息子の年齢、困りごとに合うペアレント・トレーニングが見つからず、また行き詰まってしまった私。
最終的に申し込んだのは、有料のオンライン講座でした。
高額だったので、何ヶ月も考えました。
でも、いくら調べても、他に解決策がなかった。
「もう、今の状況に合うのはこれしかない」と、思い切って決断しました。
受講してみて思ったのは、
「勇気を出して受講してよかった!」でした。
特性に合わせた声かけや、考え方のベースをしっかり学ぶことができました。
有料講座なので詳細は書けませんが、
思春期以降に診断が出て、悩んでいるお母さんにはおすすめです。
ペアレント・トレーニングは、子育ての土台だった

講座を受けてみてわかったのですが…
実はこのペアレント・トレーニングの内容、
定型発達の次男の子育てにもすごく役に立つものだったのです。
「発達特性のある子向け」だと思っていたペアレント・トレーニング。
でも実際には、子育て全般に共通するエッセンスがたくさん詰まっていました。
もちろん、受講したからといって、すぐに楽になるわけではありません。
でも、「こうすればいいんだ」と理論を理解できたことで、心がずいぶん軽くなりました。
正直、お金がかかることなので、「みんな受けてみて!」とは言いづらいですが…
もし思春期以降のお子さんの対応で困っている方がいたら、
「我が家の場合は、こんな感じだったよ!」という参考になればと思います。
もちろん、学んだだけでは何も変わりません。
「子どもへの接し方を変える」というのは、私にとってとても大変なこと…
学んだことを実践する中でのストレスもかなりありました。
でも、そこは講師の方が伴走してくれたことで、何とか頑張ることができました。
自分の感情が全然ついていかず、葛藤の毎日でしたが、次第に、息子のちょっとした変化や成長が見られるようになり、それを励みに頑張れたような気がしています。
そして何よりも、
「二度と、あの夏休みのような気持ちは味わいたくない!」
という、過去の経験が、自分の原動力になっていたように思います。
まとめ
何ヶ月も待って、「これで道がひらける!」と期待して行った発達外来。
そこで言われた医師からの心無い言葉…
それにより、息子はさらに傷つき、私も療育への道が閉ざされてしまいました。
でも、それまでも何度も絶望を乗り越えてきました。
結局、前を向いて、今の自分にできることを探し、やっていくしかありませんでした。
そこで行き着いたのが「ペアレント・トレーニング」。
そこで学んだことは、長男の困りごとの改善だけでなく、次男の子育てにもとても役に立ちました。
・小学校高学年以降で診断が出た親子
・診断は出てなくても、グレーゾーンで悩んでいる親子
きっと多いのではないでしょうか。
我が家の経験談の中で、何か1つでもヒントになることがあれば嬉しいです。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ではまた!とらすけでした🐯
↓【不登校経験談】過去記事はコチラ↓
我が家の不登校経験談①~不登校になるまで~
我が家の不登校経験談②〜不登校の原因となった担任からの叱責〜
我が家の不登校経験談③〜スクールカウンセラー〜
我が家の不登校経験談④〜不安と焦り〜
我が家の不登校経験談⑤〜先生が変われば…期待と現実〜
我が家の不登校経験談⑥〜「生きているのがつらい」息子から届いたSOS
我が家の不登校経験談⑦〜母子ともに限界だった2学期の始まり〜
我が家の不登校経験談⑧〜発達検査でADHDが判明〜
我が家の不登校経験談⑨〜ADHD診断後に療育が見つからない!高学年・不登校のリアル〜
我が家の不登校経験談⑩〜通院をやめても、少しずつ前に進んでいた〜
我が家の不登校経験談⑪〜「学校以外の道」を探し始めた日々〜
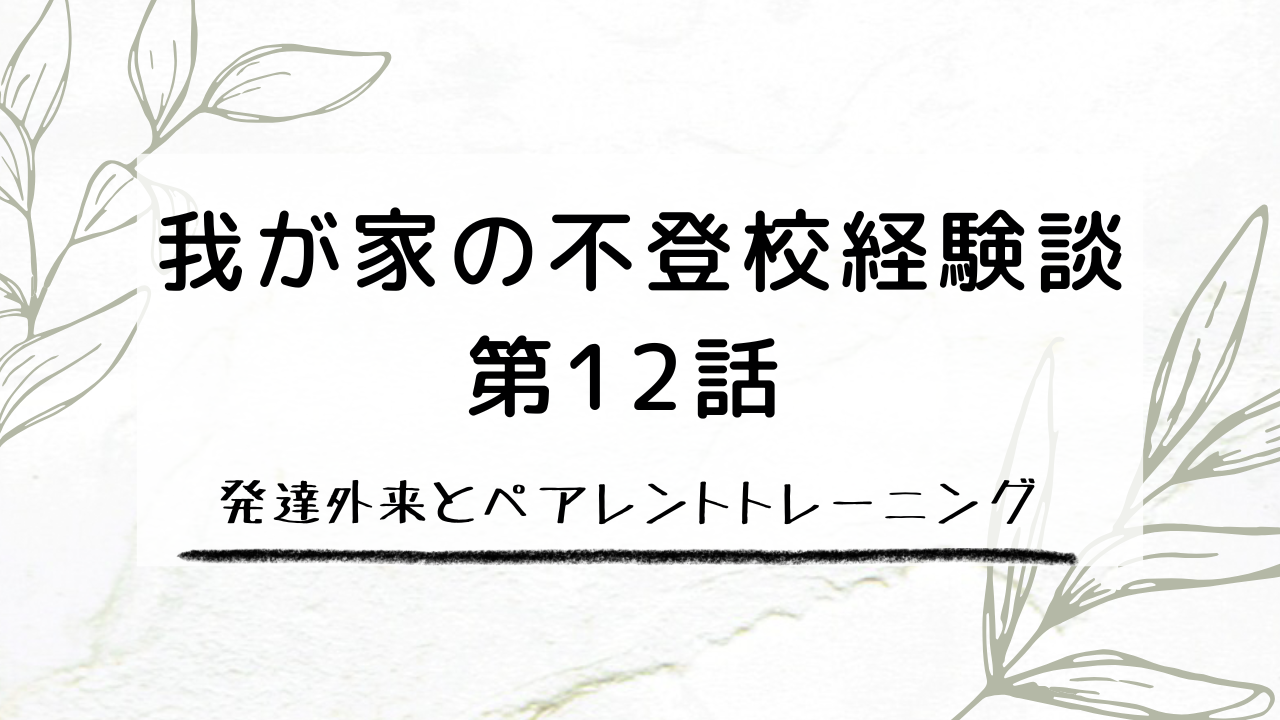

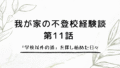
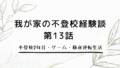
コメント