こんにちは。とらすけです🐯
»プロフィールはこちら
息子は小4で学校へ行けなくなり、小6まで完全不登校。
中1では希望のフリースクールに週1回通学、1年間継続しました。
そして現在中2。
自分の力で勉強をしたいと、フリースクールから新たな道へ切り替え中です。
小学校後半はほぼゼロ勉でしたが、今は自ら勉強をするまでに回復しました。
▼勉強に関する過去記事はコチラ▼
「【不登校】「勉強の遅れ」はどうする?不登校の子が勉強に取り組むために必要なこと」
経験談①〜⑩話の期間を乗り越え、気づけば息子が学校へ行けなくなって数ヶ月。
時間をかけて少しずつ、
「学校へ行くことがゴールじゃない」
そんなふうに割り切れるようになっていきました。
(👇ここまでの経緯は、過去の【不登校経験談①~⑩】でまとめています👇)
↓【不登校経験談】過去記事はコチラ↓
我が家の不登校経験談①~不登校になるまで~
我が家の不登校経験談②〜不登校の原因となった担任からの叱責〜
我が家の不登校経験談③〜スクールカウンセラー〜
我が家の不登校経験談④〜不安と焦り〜
我が家の不登校経験談⑤〜先生が変われば…期待と現実〜
我が家の不登校経験談⑥〜「生きているのがつらい」息子から届いたSOS
我が家の不登校経験談⑦〜母子ともに限界だった2学期の始まり〜
我が家の不登校経験談⑧〜発達検査でADHDが判明〜
我が家の不登校経験談⑨〜ADHD診断後に療育が見つからない!高学年・不登校のリアル〜
我が家の不登校経験談⑩〜通院をやめても、少しずつ前に進んでいた〜
でも心のどこかで、「じゃあ、これからどうする?」という問いがずっと頭にありました。
・家で過ごしている息子に、何かできることはないか。
・学校以外の選択肢は?
・家にいながらでも受けられる支援は?
——今回は、そんなことを模索しはじめた頃の記録です。
・不登校支援団体等の無料セミナー
・適応指導教室
・不登校支援ルーム(不登校の子の居場所、フリースーペス)
・市の教育相談
・民間のフリースクール
・その他の選択肢
色々な選択肢があるなかで、我が家に合っていたものは?
それぞれについて、経験談と感じたことを書いていこうと思います。
今回も、不登校で悩んでいる方の参考になったら嬉しいです。
無料セミナーはどんどん利用しよう

当時、私がとにかくやっていたのは、「情報を集める」こと。
ネット検索はもちろんのこと、発達・不登校支援団体の無料セミナー、専門家による無料相談など、利用できそうなものにはとにかく参加しました。
セミナーがもたらした安心感
知らないから不安になっていた
人間、自分が知っている範囲の世界で生きていれば安心できます。
でも、経験したこともない世界、聞いたこともない世界だったら…?
不安を感じますよね。
不登校も同じです。
「学校以外のルートを知らないから怖かった。」
「でも知ってみたら、希望が湧いてきた!」
「何とかなる気がしてきた!!」
まずは、自分が知っている枠を超えて、「実は他にも色々な選択肢がある」ことを知る。
当時の私は、そうすることで、少しずつ「学校へ行かないことに対する不安」を減らしていきました。
まずは参加してみる!1人じゃないから大丈夫。
当時はコロナ禍だったので、オンラインセミナーが多い時期でしたが、直接行ける所へは、実際に足を運びました。
そうすることで、情報を得るだけでなく、同じ悩みを抱えている人、自分たちよりももっと大変な思いをされている人と会い、直接お話ができました。
不登校初期は、子どもが学校へ行けなくなるなんて我が家だけ?のような気がして、とても孤独でした。でも、実際にセミナーに足を運んでみると、同じ境遇の人達が沢山いたのです。
「自分だけじゃなかった」「理解してくれる人がこんなにいたんだ」という安心感が、当時の私にとってとても励みになりました。
セミナーから広がる情報・つながり
民間セミナー以外にも、私が住んでいる地域では、不登校の親の会などが、公民館と共同主催でやっているセミナーもありました。
色々な方が、講師として来てくださりました。
・有名な不登校支援者さん
・元不登校だった当事者の方
・不登校後の進路選びに詳しい方
また、そこから市内で親の会を主催されている方とつながったり、ヒントやアドバイスをいただけたり。とても有益な時間を過ごすことができました。
このように、市のHPに載っていなくても、埋もれているイベントがあるかもしれません。
また、自分の住んでいる自治体でなくても、参加できるものもあります。
自分の地域にこだわらず、他の地域の公民館イベントもチェックしてみてください。
(我が家の地域では、市報よりも公民館だよりのほうに、セミナー情報が載っていることが多いです。)
公民館イベントをきっかけに、そこに参加されている支援団体さんが主催する別のセミナーの情報を得られれこともありますので、ぜひ足を運んでみてください。
学校以外のルートはたくさんあることを知った
私は、そのようなセミナーを通して、本当にたくさんのことを学びました。
・不登校でも、通信制高校やチャレンジ校などの進路がある
・元不登校でも、バイトや大学生活を楽しんでイキイキ過ごしている子もたくさんいる
・凸凹があっても、それぞれの得意を伸ばしてあげれば子どもは成長する
・価値観を壊すこと=視野を広げること
不安でいっぱいだった私が、「大丈夫、なんとかなる!」と思えるようになったのは、この時期に得た情報たちのおかげです。
市の支援はどうだった?

もちろん、市の施設や支援も調べ、見学や相談に行きました。
【子どもが利用する支援】と【親が利用する支援】に分けて紹介しますね。
【子どもが通える施設】
うちの地域では、市がやっている不登校児向けの施設は、この2つでした。
・適応指導教室(市内に2か所)
・不登校支援ルーム(不登校の子の居場所、フリースーペス)
適応指導教室
【適応指導教室】は市内に2箇所あり、片方は家からも通いやすかったので、期待をしながら問い合わせをしました。
しかし実際は…
2箇所といっても小学生対象の教室と中学生対象の教室で、2箇所に分かれている形でした。
おまけに、小学生対象の施設は我が家からかなり遠い場所…
それでも「行けるなら行ってほしい」と藁にもすがる思いで、見学に行きました。
息子は「行きたくない…」と拒否だったので、私だけで…
そこで言われた印象的だった言葉。
「ここは、不登校の子にとって“最後の砦”。無理に通わせて、ここもダメだったとなると、心の傷になることもあります。慎重に考えてください」
すごく納得しました。
(決して、最後の砦なわけではないのですが、市の「学校っぽい施設」としては、確かにここが最後の砦のような存在ではあると思います。)
当時の息子は、外に連れ出すのも大変な状態。
おまけに建物は市内の小学校の中にありました。
学校が怖くなってしまった息子には、とんでもなくハードルが高い場所。
活動内容も、通常の学校よりは柔軟とはいえ、時間割や勉強時間もある。
どう考えても、相当な無理をしないと行くことはできない場所でした。
すぐに諦めがつきました。
不登校の支援者の中には、学校へ戻すことをゴールと考え、適応教室へ子どもを行かせるためのアドバイスをしてくる先生もいるかもしれません。
でもその先生は違いました。
うちの息子の現状を踏まえた、現実的なアドバイスをくれました。
とても感謝しています。
不登校支援ルーム(不登校の子の居場所、フリースペース)
一方で、【市の不登校支援ルーム】は、とても穏やかで優しい雰囲気の場所でした。
時間割などの決まりはなく、不登校の子たちが自由に過ごせるスペース。
ボードゲーム、外遊び、お散歩、ただ話すだけでもOK。
行きたい時にふらっと行ける、あたたかい居場所です。
ここだけは、息子も自分から「見学行きたい」と言い、実際に足を運ぶことができました。
スタッフさんたちもとても穏やかで、本人も「ここなら行ってみたい」と感じ、利用手続きをしました。
でも——
当日になると、どうしても行けなかったのです。
その後も何度か「行ってみる」と予約を入れてみましたが、当日になるとやっぱり無理…。
そうした日が何度も続き、最終的には支援ルームに通うことは諦めました。
(結局、息子が支援ルームに通えるようになったのは、それから約1年半後のことでした。)
通えなくても受けられる支援があった
でも、通えなかったあとも、この支援ルームにはお世話になりました。
実はこの施設には、「家庭訪問のサポート」があったのです。
スタッフさんが2週間に1回、30分ほど家に来てくれて、息子の話し相手、相談相手になってくれていました。
担当になってくれたのは、若い男性スタッフさん。
息子の部屋で、雑談をしたり、ゲームの話をしたり。
時には、ゲームをしている息子の様子を横で見守ってくれたり。
息子にとって、安心できる時間をつくってくれる存在でした。
深く踏み込むことはせず、でもその子に合わせた程よい距離感で、静かに寄り添ってくれる。
そんな存在が、当時の息子にとってはとてもありがたかったのです。
「どんな自分でも受け入れてくれる大人がいる」——
その経験が、息子の心の回復につながっていったと感じています。
元担任やスクールカウンセラーとの出来事で、大人への不信感を抱いていた息子。
それでも、この訪問支援スタッフさんとの時間は、大人に対する信頼感を取り戻す、きっかけのひとつになったと思います。
不登校の子の中には、まだ人に会える状態ではない子や、訪問自体がストレスになる子もいます。
我が家の場合はプラスに働きましたが、皆さんのお子さんにも合うとは限りません。
「こういうパターンもあるんだなぁ」くらいの気持ちで読んでもらえたら嬉しいです。
【親が相談できる施設】
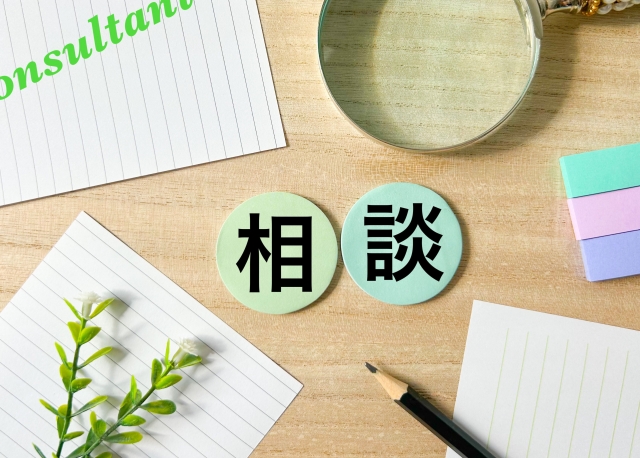
市の教育相談
市の教育相談にも行っていました。
でも、こちらは「相談して状況がよくなる」というものではなく…
モヤモヤすることもたくさんありました。
不登校について詳しくない相談員さんだったのもあり、「そんなの分かってるよ!」というアドバイスをされることもしばしば。
でも我が家の場合は、過去に、スクールカウンセラーにさえ不登校に全く理解のない対応をされた経験があったので、正直、「市の相談機関って、そんなもんよね…」という感覚でした。
・月に1回、ただただ自分の愚痴を吐き出せる場。
・愚痴を吐くことで、自分の気持ちを整理する場。
そんな「荷下ろしの時間」だと思って割り切って通っていました。
でも、解決にはならなくても、不登校の母にとってそういう時間や場所ってめちゃくちゃ大事です。
不登校の母は、とても孤独を感じることが多いです。
私は、仲の良いママ友にも話を聞いてもらってはいましたが、それでもやっぱり、不登校の本当のリアルな現実まではなかなか話せませんでした。
たいしたアドバイスや、解決策は見つからなくても、不登校生活を赤裸々に吐き出せる相手や場所とつながっておくことは、長い目で見てとても大事だと思います。
逆に、色々なアドバイスをしてくれる人だと、かえって苦しくなってしまうこともあります。
私の場合、下手なアドバイスをされず、淡々と話して帰ってこられる相談員さんというのが、合っていたのかもと、今となっては思います。
民間のフリースクール

次は、民間のフリースクールです。
今はフリースクールも通学型だけではなくオンラインでどこでも入学できたりと、選択肢もさらに広がってきています。
でも大事なのは、
お子さん本人が「本当にフリースクールに入りたいと思っているか?」です。
「学校へ行けない」→「フリースクールなら行ける」とは限りません。
親の希望ではなく、お子さんの気持ちを第一に考えてあげてくださいね。
通学型フリースクール
我が家の場合、まずは通学型のフリースクールを検討しました。
しかし、現実的に通いやすいスクールはなかなかなく…。
1つだけ、家からかなり近いスクールがあったので見学に行ったものの、月謝が高額…。
そして何よりも、息子本人が行きたそうではなかった。
申込みをしても続かないなと感じ、我が家は行かない選択をしました。
オンラインフリースクール
次に候補に上がってくるのがオンラインフリースクールかと思います。
我が家の場合、息子専用のパソコンがなかったので、この時点では、リアルに通えるフリースクールばかり探していました。
でもこの後、パソコンを買うことになり、それを機に【オンラインフリースクール】も選択肢に入ってきました。
実際に、あるオンラインフリースクールに入会し、そこでオンライン上の友達ができ、1年ぶりに息子に笑顔がもどってくることになるのです。
オンラインフリースクールについては、経験談シリーズが終わってから、詳細を書いていこうと思います。
今は外に出られなくても、たくさんの選択肢がある時代です。
今はまだオンラインでも参加するのが難しい子もいると思います。
うちの息子も、不登校初期の状態では、オンラインでも入会できなかったと思います。
どんな選択肢があるのか情報を持っていれば、すぐに利用できない情報だったとしても、子どもが回復してきた時に、どこかでピッタリと合うタイミングがくるかもしれません。
「今の時代はこんな選択肢もあるんだなー」「そういう子もいるんだなー」くらいの気持ちで、気軽に情報収集をしてみてほしいです。
【不登校支援】以外でも子どもは成長できる
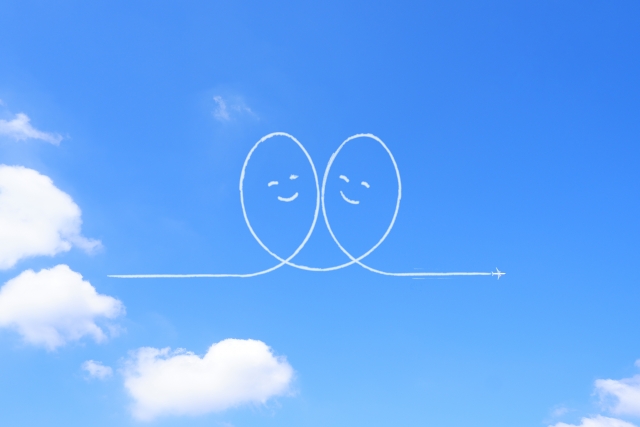
そんなある日。
毎日YouTubeばかり見ていた息子が、ふと「youtuberになりたい」と言い出しました。
今の時代は一般人でもYoutuberになる時代、ましてや毎日Youtubeを見て過ごしている息子。
「Youtuberになりたい」発言には、何も驚きませんでした。
驚いたのはその後…
「だから、動画編集を習いたい」と言ったんです。
半年前は「生きているのがつらい」と言っていた子。
その子が自分から、「やりたいこと」を口にしたのです。
色々なセミナーを受けていた私。
ちょうど、オンラインで「動画編集」の習い事があると知ったばかりでした。
すぐに体験を申し込み、お試しレッスン。
息子も「楽しい!」と、すぐ入会。
そこから2年間も続けることができました。
たまたまですが、担当の先生は、なんと元不登校の子のお母さんでした。
「先生の家のお兄ちゃんも不登校だったんだって!でも今はバイト頑張って、行きたかった旅行に行ってるんだって!」と、嬉しそうに話してくれた息子。
その希望に満ち溢れた顔は、今でも忘れられません。
親だけでなく、子ども自身もとても孤独だったんだと思います。
「学校へ行けてないのは自分だけじゃなかったんだ」という安心したような表情でした。
頭痛でレッスンをドタキャンすることも何度かありましたが、不登校に理解のある先生だったので、いつも温かく対応してくださいました。
苦しい中でも、このような温かなこ゚縁に感謝の気持ちでいっぱいです。
このような、
「どんな自分でも受け入れてくれる大人がいる」という経験は、
息子の心の回復につながったと感じています。
まとめ
振り返ると、不登校の支援は本当にたくさんの選択肢があります。
「学校へ行けない=すべてが終わり」では、決してありません。
でも、それを知るにはまず「情報を拾いに行く」ことが大事だと感じました。
すぐに使える情報じゃなくても、後で「あの時知っておいてよかった」と思える日がきます。
ただ1つ。注意して欲しいことがあります!
たくさんの情報が手に入るのはメリットである反面、デメリットもあります。
自分の心が辛くなる情報、我が子の性格や状態にはどう考えても合わない情報、逆効果と感じる支援方法に出くわしてしまうこともあります。
私の経験談も、合わないと感じる方もいると思います。
そんな時は、母親の直感を信じてみてください。
「この情報は我が子には違う」と感じたら、スルーする勇気も大事です。
どうか、「うちの子に合う支援」を焦らず探していってください。
そしてそんな中で、子ども自身の中から「やってみたい」と言う気持ちが出てきたときには、そっと背中を押してあげてほしいです。
「やってみたい」は、きっと、生きる力になります。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ではまた!とらすけでした🐯
↓【不登校経験談】過去記事はコチラ↓
我が家の不登校経験談①~不登校になるまで~
我が家の不登校経験談②〜不登校の原因となった担任からの叱責〜
我が家の不登校経験談③〜スクールカウンセラー〜
我が家の不登校経験談④〜不安と焦り〜
我が家の不登校経験談⑤〜先生が変われば…期待と現実〜
我が家の不登校経験談⑥〜「生きているのがつらい」息子から届いたSOS
我が家の不登校経験談⑦〜母子ともに限界だった2学期の始まり〜
我が家の不登校経験談⑧〜発達検査でADHDが判明〜
我が家の不登校経験談⑨〜ADHD診断後に療育が見つからない!高学年・不登校のリアル〜
我が家の不登校経験談⑩〜通院をやめても、少しずつ前に進んでいた〜
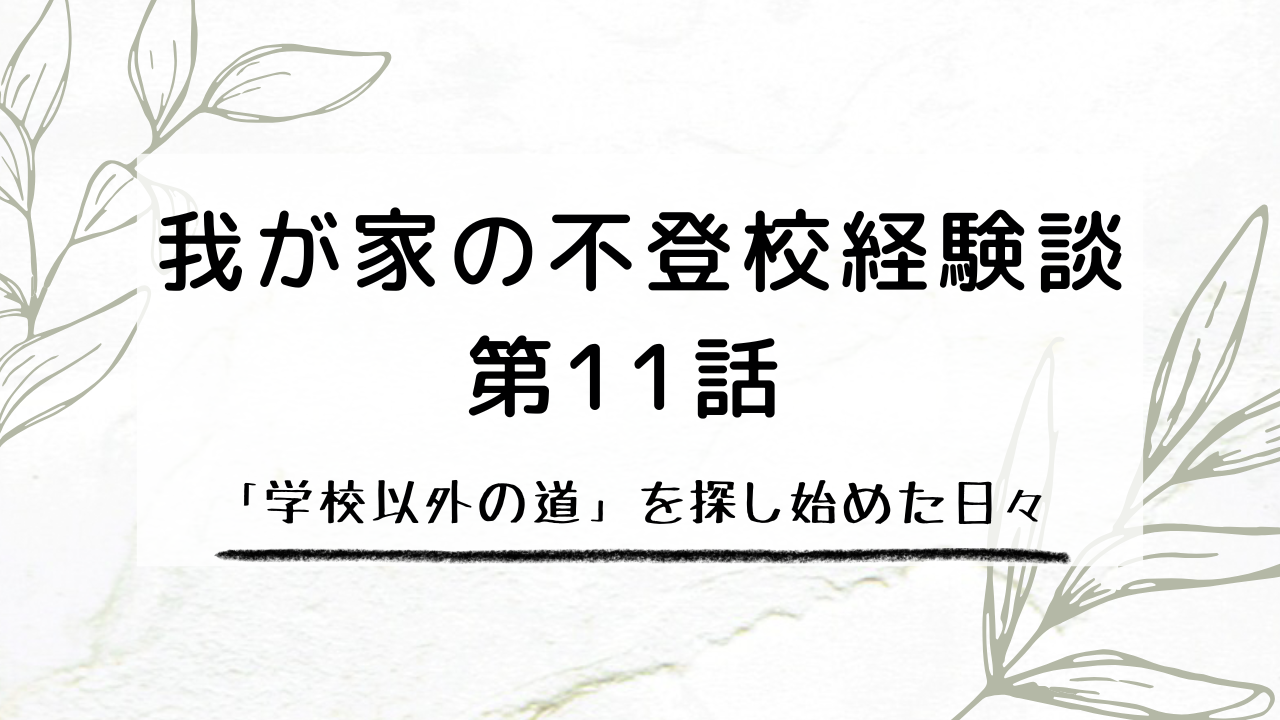

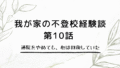
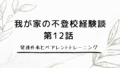
コメント