こんにちは。とらすけです🐯
»プロフィールはこちら
息子は小4で学校へ行けなくなり、小6まで完全不登校。
中1では希望のフリースクールに週1回通学、1年間継続しました。
そして現在中2。
自分の力で勉強をしたいと、フリースクールから新たな道へ切り替え中です。
小学校後半はほぼゼロ勉でしたが、今は自ら勉強をするまでに回復しました。
勉強に関する過去記事はコチラ👉️「不登校〜勉強の遅れはどうする?〜」
前回の記事では、ADHD診断後の療育施設を探した時のことを書きました。
療育を受けられそうな病院は見つかったものの、初診予約は数カ月先。
今回は、病院受診までの数カ月間の出来事について、書いていきたいと思います。
今回も、不登校で悩んでいる方の参考になったら嬉しいです。
↓【不登校経験談】過去記事はコチラ↓
我が家の不登校経験談①~不登校になるまで~
我が家の不登校経験談②〜不登校の原因となった担任からの叱責〜
我が家の不登校経験談③〜スクールカウンセラー〜
我が家の不登校経験談④〜不安と焦り〜
我が家の不登校経験談⑤〜先生が変われば…期待と現実〜
我が家の不登校経験談⑥〜「生きているのがつらい」息子から届いたSOS
我が家の不登校経験談⑦〜母子ともに限界だった2学期の始まり〜
我が家の不登校経験談⑧〜発達検査でADHDが判明〜
我が家の不登校経験談⑨〜ADHD診断後に療育が見つからない!高学年・不登校のリアル〜
メンタルクリニック通院ー親の目的と子の目的

不登校になって受診したメンタルクリニック、そこで息子はADHDと診断されました。
医師のアドバイスもあり、まずは、すぐ学校へ行けるようにすることを目的にするのではなく、
「将来、学校へ戻れたときに、少しでも過ごしやすくなるように」と、
メンタルクリニックとは別に、療育を受けることができる病院を予約しました。
メンタルクリニックでは気持ちを和らげる漢方が処方されていましたが、数ヶ月飲み続けても特に薬の効果は感じられず…
最終的には医師と相談のうえ、服用をやめました。
親としては正直な所、「病院へ行くことで得られる安心感」がありました…
でも、息子本人は…?
「なんでメンタルクリニックに行かなきゃいけないの?」
「ぼくは別に何も困ってないのに」
と言うように。
そして、通院そのものを嫌がるようになったので、クリニックへ行くのはやめることにしました。
学校と同じく、本人が行きたくないのを無理やり連れて行くことで、また親子関係が悪化すると感じたからです。
通院をやめたのに良い変化が出てきた

通院も、服薬もやめたけれど、不思議と息子の様子は少しずつ落ち着いてきました。
気づけば、以前のようなひどいパニックや幻覚のような状態は減っていきました。
後になって振り返ると、私自身が
・怒ったり、注意する回数を減らしたこと
・できるだけ褒める回数を増やしたこと
・自分で良くないと感じた対応を、小さなことから少しずつ変えていったこと
が大きかったように思います。
一方で、息子は反抗的な態度をとることが増えてきました。
一見悪化しているように聞こえるかもしれませんが、私はこれを、「良い変化」と捉えていました。
なぜなら…
それまでの私達親子は、私の言うことが絶対で、息子が自分の気持ちを言葉にして伝えることは少なかったから。
癇癪やグズグズと泣いて反抗することはあっても、私に面と向かって
「今の自分の気持ち」
「お母さんのこういうところがムカつく」
「ぼくはこう思う!」
と言うことはほとんどありませんでした。
このように自分が感じている気持ちや意見を、自分の言葉で返せるようになったことは、本来あるべき子どもの姿に近づいているように思えたのです。
もちろん、反抗されればムカッとするし、言い返してしまうことも多々ありました。
でもその後に、
・なんで息子はあんな態度をとったんだろう
・本当はどうしてほしかったんだろう
と、これまでにはなかった視点で息子の気持ちを考えられるようになっている自分がいました。
まだまだ感情がついていかず、イライラをぶつけてしまうことも多々ある時期でしたが、そんな中でも、小さいことから変えていく意識をもつだけでも、自分の中で小さな成長が始まっていました。
そして、それに伴って、息子にも見えない変化が少しずつ起こっていたのです。
毒親だった私でも変われた「少しずつ」の積み重ね

私は自分で「毒親だった」と思っています。
すぐ怒鳴る、正論を押し付ける、子どもにも自分の価値観を押し付ける……。
でも、そんな私でも少しずつ変わっていけました。
もちろん、何度も何度も同じ失敗を繰り返しました。
「またやっちゃった……」と思うことばかり。
でも、それでも
・前より少し怒らずにいられた
・ちょっとしたことを褒めることができた
・注意する前に一呼吸おいて考えられる回数が少し増えた
そんな自分の小さな変化を感じられるようになっていったのです。
息子との会話が少しずつ変わってきた
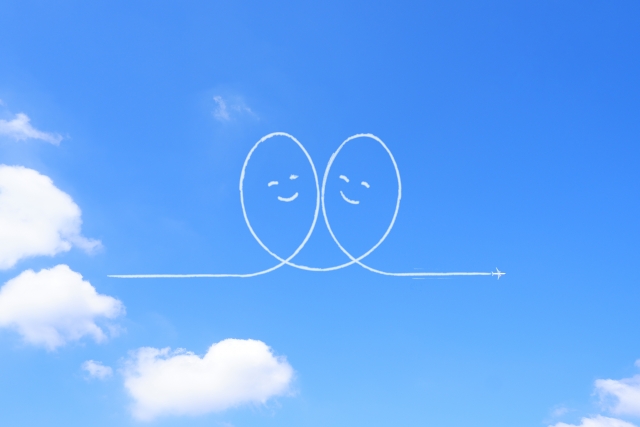
また、息子と会話ができる時は、なるべく息子の話を否定せずに聞こうと意識していました。
・興味のないゲームやYouTubeの話でも、できるだけ相槌を打ちながら聞く。
・学校や勉強のことなど「私がしたい話」ではなく、「息子がしたい話」をする。
・会話は<子ども9割:親1割>
・正論やアドバイスは言わない。
その効果か、9月に入ったころ、
息子が初めて「元担任からの叱責事件」のことを自分の口から話してくれたのです。
事件から4ヶ月。
やっと自分の口から、自分の言葉で、辛かった体験を話すことができたのです。
私の、話を聞く姿勢の変化を感じたのかなと思います。
ものすごく大きな前進でした。
それ以外にも、
・「自分は怒られてばかり」
・「弟ばかり褒められている」
・「自分には褒められるところがない」
など、これまで抱えていた悲しい気持ちや不満を、少しずつ言葉にしてくれるようになりました。
子どもの価値観を受け入れる勇気

その頃の息子は、
「勉強する意味がわからない」
「なんで全員並んで同じことをしないといけないの?」
——そんな疑問も口にするようになりました。
昔の私なら、理由となりそうな正論を並べて、言い返していたと思います。
でも、不登校についての情報を集める中で、私の中の「常識」や「当たり前」が少しずつ緩んでいきました。「そう思うこともあるよね…」と、自分とは違う意見も、少しずつ受け入れられるようになっていったのです。
この頃から、私のゴールも変わっていきました。
「学校へ行かせること」ではなく、
息子自身が「生きててよかった」と感じられる人生を送ること
「俺は幸せだぁぁー!!」と、息子自身が満足する人生を送ること
それこそが本当に目指すべき場所だと、心から思えるようになっていきました。
子どもの人生の主役は、「親」ではなく「子ども自身」
と言う、本来なら当たり前のことに気づき、実感するようになったのです。
ルールをゆるめる勇気

もちろん、そう気づいて、すぐ自分の言動を変えられたわけではありません。
そこに至るまでに、たくさんの葛藤がありました。
「学校へ行くことがゴールではない」と思えるようにはなったけれど…
その代わりにたくさんの「せめて◯◯」の気持ちが、顔を出し始めました。
「学校へ行けなくてもいい。でも、せめて…」
・他の子が学校へ行ってるい時間は、家で勉強しよう
・他の子が学校へ行っている時間は、ゲームやYouTubeは禁止
・運動しよう
・日光を浴びるために外に出よう
そんな気持ちが強く、当時の私は、不登校生活におけるルールをたくさん設けていました。
でも、ADHDの特性もあり、息子は時間通りに動くことやルーティンを守ることが元々苦手。
それに加えて、不登校になってから特性がさらに強く出るようになってしまい、元々できていたことさえもできなくなっている状態でした。
そのたびに私はイライラし、怒鳴ってしまい、結局は最悪な雰囲気に……。
じゃあ怒鳴らず、優しく言い聞かせれば?
…そのくらいで解決したら、苦労はしません!!
でも、「ルールを守らせるたびにこんなに怒ってばかりだったら、せっかく前進してきたのに、また逆戻りだ」——あの苦しかった夏休みが、その後の私の原点になりつつありました。
イライラを息子にぶつけてしまう度に、何度もその原点に戻り、何が一番大事か、どうしたいのかを繰り返し考えました。
今大事なことは、勉強でも、時間を守ることでもない。
他の子と同じ生活をさせることでもない。
息子の心を元気にすること。
心の傷を治すこと。
そのためには、母子関係の修復が最優先でした。
私は自分の中の「こうあるべき」「せめてこれだけは」という思いを、一つずつ手放していきました。
「勉強しないなら、せめて家の手伝いを。」
→「手伝いもしないなら、せめてNHK for Schoolを見よう。」
→「ゲームをするなら、せめてマイクラにして…」
→最後に残ったのは…
「健康で、笑って生きてくれていればいい」でした。
——そんな風に“せめてシリーズ”を少しずつ緩めていったのです。
この時期に私が意識して取り組んだことまとめ
この頃の私自身が少しずつできるようになってきたこと。
・ドカーンと怒鳴らずに対応できる回数が増えた
・注意する前に、一呼吸おいて考えられるようになった
・小さなことでも褒めるようになった
・少しルールを破られても、すぐ怒らずに様子を見ることができた
・ゲームやYouTubeをだらだら見ていても、夕飯までならOKとルールを緩めることができた
・子どものしたい会話を、否定せずに聞くよう意識した
・子どもの感情に巻き込まれすぎないよう、少し距離をとる意識を持つようになった
すぐに結果に結びつくわけではありませんが、でもこれらの変化は、確実に私たち親子の間にある空気を和らげてくれたと感じています。
今だから言えること

何度も言いますが、不登校の対応に、絶対これ!と言う「正解」はありません。
正直な所、その時その時の「わが子の状態」を見つめて、「その時できること」をやってみるしかないと思います。
「やってみる」と聞くと、何か「やることを増やす」イメージがありますが、
私が不登校の対応全体をしてきてやってよかったこととは、
やることを「増やす」よりも「手放してみる」こと。
握りしめているもの、こだわっているものを一旦「手放してみる」
自分が常識や普通と思い込んでいること、世間体、一般論、このような自分にとって絶対と思っていることを、少しずつ緩めてみてください。
最初はとても不安だとは思います。
でも長い目で見ると、手放しても大丈夫なものって実はたくさんありました。
「どんな過ごし方が“正しい”か」ではなく、
“どんな自分でも親は受け入れてくれる”と、安心して穏やかに過ごせる日々を積み重ねる。
それが、遠回りに見えて、一番の近道だったと思っています。
受け入れてもらえる安心感が育ってくると、不思議と子ども自ら考え、感じ、動き出し始めました。
まとめ
息子の不登校をきっかけに始まった、私たち親子の「関係の再構築」。
通院や薬だけでは変わらなかった息子でしたが、親である私自身の意識と関わり方の変化によって、少しずつ落ち着きを取り戻していきました。
息子の反抗的な態度さえも、私達親子にとってそれは「自分の気持ちを言えるようになってきた」という、大切な成長の一歩でした。
子どもの価値観や感じ方を否定せずに受けとめようとする中で、私の中にあった「常識」や「べき論」も、少しずつ手放すことができました。
不登校の対応に絶対の正解はありません。
「我が子にとっての正解」を見つけていく旅です。
時間はかかるかもしれないけど、
「すぐ結果が出ないこと」や「小さな変化」が、
本当は一番大切なプロセスなのかもしれません。
焦らなくて大丈夫。
親も子も、「今できる小さなこと」を少しずつ見つけて積み重ねていけば、きっと前に進んでいけます。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ではまた!とらすけでした🐯
↓【不登校経験談】過去記事はコチラ↓
我が家の不登校経験談①~不登校になるまで~
我が家の不登校経験談②〜不登校の原因となった担任からの叱責〜
我が家の不登校経験談③〜スクールカウンセラー〜
我が家の不登校経験談④〜不安と焦り〜
我が家の不登校経験談⑤〜先生が変われば…期待と現実〜
我が家の不登校経験談⑥〜「生きているのがつらい」息子から届いたSOS
我が家の不登校経験談⑦〜母子ともに限界だった2学期の始まり〜
我が家の不登校経験談⑧〜発達検査でADHDが判明〜
我が家の不登校経験談⑨〜ADHD診断後に療育が見つからない!高学年・不登校のリアル〜
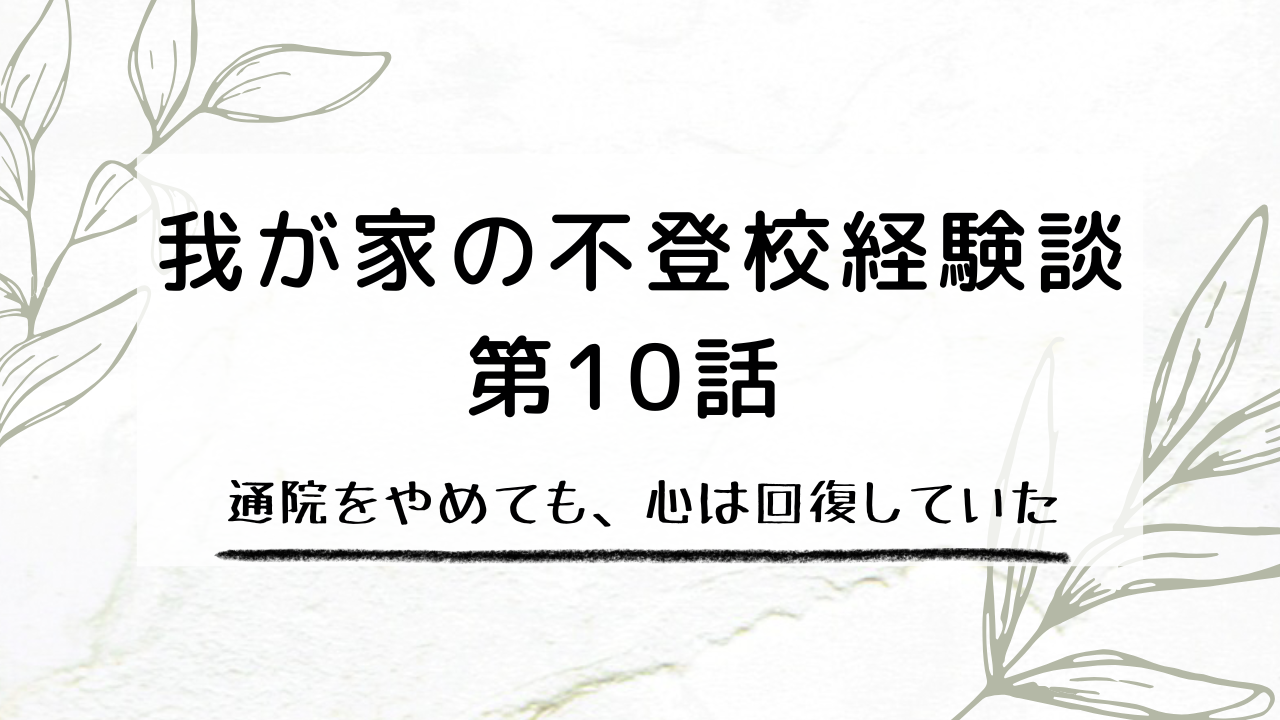

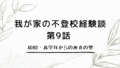
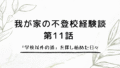
コメント